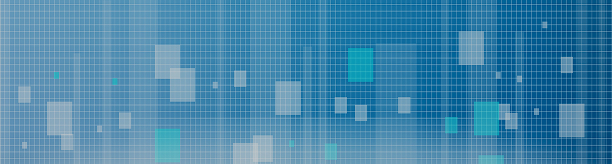- share :
「DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性は理解しているが、具体的に何から手をつければ良いのか…」
「他社の成功事例は聞くけれど、自社にどう応用すればいいか見当がつかない」
中小企業の経営者やDX推進担当者の方の中には、このような悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。変化の激しい現代において、企業の持続的な成長のためにDXは不可欠な要素となりつつあります。しかし、その導入や推進には多くの課題が伴うことも事実です。
本記事では、意外かもしれませんが、今から約1200年前、平安時代初期に活躍した偉人、空海のエピソードから現代のDX推進に通じるヒントを探ります。
真言宗の開祖として知られる空海ですが、彼の功績は「仏教の教えを説いて回った宗教家である」というだけに留まりません。彼が宗教を広めるために行った「高野山」の建立は、国家規模ともいえる規模の壮大なプロジェクトでした。現代の視点から見れば、革新的な資金調達力、卓越した人材育成力、そして強力なリーダーシップを備えた空海だからこそ成し遂げることができた一大事業だったのです。
空海が成したこの世紀の大事業は、1200年という時を超えて、現代企業がDXを成功裏に導く上で、非常に示唆に富んでいます。この記事を通じて、空海の足跡を辿り、貴社のDX戦略を成功に導くための「普遍的な原則」を学び取っていただければ幸いです。
高野山プロジェクト:1200年前の壮大な「変革」事業

「DX」が目指す変革とは、新しい技術導入が目的なのではありません。DXの目的は、「デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化を変革し、新たな価値を創造すること」を目指すものです。変革はあくまでも「新しい価値創造」を達成するための手段なのです。
この視点に立って考えると、空海による高野山の建立は、まさに「仏教の教えを人々に広める」という目的を達成するために、何もない場所に「祈りの聖地」を作り上げるという、歴史的な「変革プロジェクト」であったと言えるのです。
なぜ高野山建立がDXのヒントになるのか?
空海が生きた平安時代初期は、当然ながらコンピューターもインターネットも存在しません。そのため、現代のDXとは文脈が大きく異なっています。しかし、都から遠く離れた険しい山上に、壮大な宗教都市を築き上げるという革新的な挑戦は、現代のDXに通じるものがあります。
プロジェクトには、現代のDX推進が直面する課題と共通する要素が多く含まれているのです。まずは、なかでも重要な課題をまとめてみましょう。
- 莫大な資金の調達:大規模な建立プロジェクトには巨額の費用が必要だった
- 多様な専門人材の確保と育成:宗教者だけでなく、建築、土木、芸術など、多岐にわたる分野の専門家が必要不可欠だった
- 前例のない事業への挑戦:既存の枠組みにとらわれない、全く新しい価値を持つ場を創造しようする挑戦だった
- 関係者の合意形成と推進力:天皇や貴族だけでなく、広範な人々の理解と協力を得てプロジェクトを進めなければならなかった
これらの課題に対し、空海がどのように取り組み、乗り越えていったのか。これを紐解くことは、現代のDX推進における資金調達、人材育成、組織変革、そしてリーダーシップのあり方を考える上で、貴重な学びを与えてくれるのです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義の再確認
ここで改めて、本記事の重要な概念であるDXについて振り返りましょう。DXとは、単に業務をデジタル化すること(デジタイゼーション)や、特定の業務プロセスをデジタル技術で最適化すること(デジタライゼーション)を指す言葉だけではありません。
経済産業省の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。(引用:デジタルガバナンス・コード2.0/経済産業省)」とされています。
DXをこのように広義の意味で捉えれば、空海の高野山建立は、現代のDXに通じる社会や人々の価値観に変革をもたらす試みであったと解釈できるでしょう。
共感を力に|空海流「資金調達」の現代的意義

DX推進において、初期投資や継続的な運用にかかるコストは中小企業にとって大きなハードルになりがちです。
空海は、金融システムが未発達な時代に、どのようにして高野山建立という巨大プロジェクトの資金を調達したのでしょうか。その手法は、現代の資金調達にも通じる重要な示唆を含んでいます。
「勧進」共感を基盤とした資金調達モデル
弘仁7年(816年)、嵯峨天皇から高野山の地を賜った空海ですが、実際の建立には天皇からの直接的な財政支援だけでは到底足りませんでした。記録によれば、空海は「勧進(かんじん)」と呼ばれる手法を積極的に用いたとされています。
「勧進」とは、事業の意義や目的を人々に説き、その趣旨に賛同・共感した人々から自発的な寄付(浄財)や労力の提供を募る活動です。空海は、高野山がもたらす価値(鎮護国家、仏法興隆、衆生済度など)を熱意をもって語り、貴族や他の僧侶だけでなく、広く一般の人々にも協力を呼びかけたのです。
現代ビジネスに置き換えれば、「特定のパトロンに依存するのではなく、プロジェクトのビジョンへの共感を基盤として、広範なステークホルダーから支援を集めた」と言えるでしょう。これは、現代のクラウドファンディングや、理念に賛同する企業・個人からの投資(インパクト投資など)などと共通しています。
DX推進における「共感型」アプローチの重要性
現代の企業がDXを進める上でも、この「共感」を基盤としたアプローチは極めて重要です。
それは、DXプロジェクトでは単に予算を確保するだけでなく、「なぜやるのか」という意義を共有し、関係者の「共感」を得て共に変革を進める姿勢が、成功確率を高める鍵となるからです。ここでは、特に重要となる2つのポイントを解説します。
社内ステークホルダーの巻き込み
DXはIT部門だけの仕事ではありません。経営層はもちろん、現場の従業員一人ひとりが「なぜDXが必要なのか」「DXによって自社の未来がどう変わるのか」を理解し、共感することが、変革を推進する大きな力となります。空海も会社という単位ではありませんが、高野山建立というプロジェクトにかかわる人々を巻き込むことで、前代未聞のプロジェクトを進めていきました。
経営者は、空海のようにDXのビジョンと意義を熱意をもって語り、社内の共感を醸成する必要があるのです。
社外ステークホルダーとの連携
顧客、取引先、地域社会といった社外のステークホルダーに対しても、自社のDXがどのような価値を提供するのかを伝え、理解と協力を得ることで、新たなビジネスチャンスやパートナーシップが生まれる可能性があります。空海も僧侶や熱心な信者など仏教界にかかわる人びとだけでなく、その外側に位置するようなアクターにまで「共感」を伝えていきました。
現代においても、特にサプライチェーン全体の効率化を目指すDXなど、自社だけでなく広範囲に影響を及ぼすDXプロジェクトの成功を目指す場合には、関係各社の協力が不可欠です。

執筆者
DXportal編集長
町田 英伸
自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。