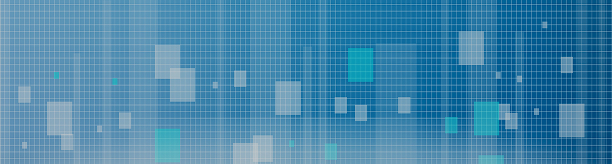- share :
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が多くの企業にとって重要な経営課題となる中、その有効な手段としてSaaS(Software as a Service)の利用が急速に拡大しています。
初期投資を抑えて迅速に導入できるうえに、常に最新の機能を利用できるSaaSは、業務効率化や新たな働き方の実現に大きく貢献する可能性を秘めています。特にリソースの限られる中小企業にとっては魅力的な選択の一つです。
しかし、その利便性の陰には、見過ごすことのできないリスクが潜んでいることを認識しておかなければなりません。実際に、設定の不備や管理体制の甘さから、情報漏洩やサービス停止といった問題が発生するケースが後を絶ちません。
本記事では、SaaSを導入・利用する際に中小企業が特に注意すべきリスクと、それらを回避し、SaaSのメリットを最大限に引き出すための具体的な対策について解説します。
DX推進を加速させるSaaSの役割

現代のビジネス環境において、SaaSは単なるITツールではなく、企業のDX推進を加速させるための重要な基盤として認識されるようになっています。インターネット経由でソフトウェア機能を利用できるSaaSは、従来のパッケージ型ソフトウェアと比較して、多くのメリットを中小企業にもたらします。
まず、サーバー構築やソフトウェアのインストールといった手間が不要であり、初期投資を大幅に抑えて迅速に導入できる点が挙げられます。また、月額や年額のサブスクリプションモデルが主流であるため、利用状況に応じたコスト管理がしやすいことも利点でしょう。
さらに、機能のアップデートやセキュリティパッチの適用は基本的にベンダー側で行われるため、企業側は運用管理の負担を軽減できます。これにより、中小企業は限られたITリソースを、より戦略的な分野へ集中させることが可能となるのです。
加えて、インターネット環境があれば場所を選ばずにアクセスできるため、テレワークやハイブリッドワークといった多様な働き方を支える基盤としても機能します。
これらのメリットから、多くの企業が会計、人事労務、顧客管理(CRM)など、様々な業務領域でSaaSの活用を進めており、DX実現に向けた重要なステップとして位置づけています。
便利さの裏に潜むSaaS利用のリスク

手軽に導入できるうえに、多くのメリットをもたらしてくれるSaaSですが、注意点もあります。その利用には様々なリスクが伴うのです。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じなければ、経営に深刻なダメージを与えかねません。
ここでは、中小企業が特に注意すべきリスクについて解説します。
セキュリティリスク:情報漏洩や不正アクセスの脅威
SaaS利用における最大のリスクの一つがセキュリティ問題です。自社でデータを管理するオンプレミス環境とは異なり、SaaSは企業の重要な情報資産を外部のクラウド環境に預けることになります。このため、以下のような脅威に常に晒されていることを認識しなければなりません。
これらのセキュリティインシデントが発生した場合、企業は顧客や取引先からの信頼失墜、損害賠償請求、事業継続の危機といった深刻な事態に直面する可能性があります。
設定ミス・脆弱性による情報漏洩
情報処理推進機構(IPA)が選ぶ「情報セキュリティ10大脅威」では、毎年のようにクラウドサービスの設定不備や脆弱性を突いた攻撃が上位にランクインしています。
アクセス権限の設定ミスや公開範囲の誤設定など、利用企業側の不注意が原因で、機密情報や個人情報が意図せず外部に公開されてしまうインシデントが発生しているのです。
不正アクセス
推測されやすいパスワードの使用、パスワードの使い回し、フィッシング詐欺による認証情報の窃取などを原因とする不正アクセスは後を絶ちません。
一度不正アクセスを許すと、機密情報の窃取、データの改ざんや削除、深刻な被害につながる恐れがあります。
内部不正・ヒューマンエラー
悪意を持った従業員による情報の持ち出し、操作ミスによる情報漏洩・消失といった内部要因のリスクも考慮する必要があります。
また、退職者のアカウントが削除されずに放置されているケースは不正アクセスの温床となる可能性があります。
運用リスク:サービス停止やデータ消失の可能性
SaaSは、サービスを提供するベンダー企業によって運用されているため、その利用継続性や安定性はベンダー側の状況に左右されます。これは、自社でシステムを管理する場合とは異なる種類のリスクと言えるでしょう。
サービス継続性に関するリスク
ベンダー側のサーバー障害やメンテナンス、あるいは自然災害など様々な事情によって、SaaSが利用できなくなるリスクがあります。総務省がガイドラインを通じて注意喚起している通り、基幹業務で利用しているサービスが停止した場合は企業の事業活動に直接的な打撃を与える懸念があります。
さらに、ベンダーの経営方針や事業戦略の都合により、機能や料金体系が変更されたり、サービス自体が終了したりする可能性も考慮する必要があります。特定のSaaSへの依存度が高い企業の場合は、代替策の検討や業務フローの大幅な見直しを迫られるなど、大きな影響を受けることになるでしょう。
データ消失のリスク
多くのSaaSでは、データのバックアップ体制が整えられていますが、バックアップの範囲、実施頻度、そして万が一の際の復旧手順はベンダーごとに異なります。
ベンダー側で大規模なシステム障害が発生した場合など、何らかの理由で大切なデータが消失してしまうリスクはゼロではありません。また、利用者側の操作ミスによって重要なデータを削除してしまった場合に、これまでの自社システムであれば復旧できていたものが、復旧できない可能性もあります。
コストリスク:想定外の費用発生
導入時のコストメリットが魅力のSaaSですが、サービス継続性とも関連して、運用を進める中で想定外のコストが発生するケースがある点にも注意が必要です。
追加費用の発生
無料プランや低価格プランでSaaSを導入したものの、必要な機能が有料オプションであったり、利用ユーザー数やデータ容量の増加に伴って上位プランへの移行が必要になったりすることで、当初の想定よりもコストが膨らむことがあります。
サブスクリプション管理の煩雑化
複数のSaaSを利用する場合は、管理が煩雑になりがちです。特に、それぞれの契約更新時期や支払い方法が異なっている場合は、その管理に無駄な工数がかかってしまうことも考えられます。また、管理が煩雑になると、利用しなくなったSaaSの解約忘れなどにより、無駄なコストが発生し続ける可能性もあります。
中小企業庁の調査などでも、ITツール導入におけるコスト管理の難しさが課題として挙げられることがあります。
ベンダーロックインと依存のリスク
特定のSaaSを長期間利用し、業務プロセスがそのサービスに深く組み込まれていくと、他のサービスへの乗り換えが困難になる「ベンダーロックイン」の状態に陥ることがあります。データの移行が複雑であったり、従業員が新しいツールに慣れるための再教育コストが発生したりするためです。
この状態になると、ベンダー側の値上げやサービス内容の変更があった場合でも、受け入れざるを得なくなる可能性が高まります。また、サービス継続性とも関連して、ベンダーの経営状況が悪化したり、事業方針が変更されたりした場合の影響も受けやすくなってしまうでしょう。
法令・コンプライアンスリスク
SaaSを利用する際には、関連する法令やガイドラインを遵守する必要があります。
利用規約
多くの場合、詳細な利用規約が定められており、データの取り扱い、禁止事項、免責事項などが記載されています。これらを確認せずに利用を開始すると、意図せず規約違反を犯してしまったり、トラブル発生時に不利な立場になったりする可能性があります。
個人情報保護
顧客情報や従業員情報などの個人情報を取り扱うSaaSを利用する場合、個人情報保護法を遵守しなければなりません。個人情報保護委員会が公表しているガイドラインなどを参考に、データの国外移転の有無や、ベンダーにおける安全管理措置などを確認する必要があります。特に、データの保存場所が国外である場合、移転先の国の法制度なども考慮に入れる必要があります。

執筆者
株式会社MU 代表取締役社長
山田 元樹
社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。