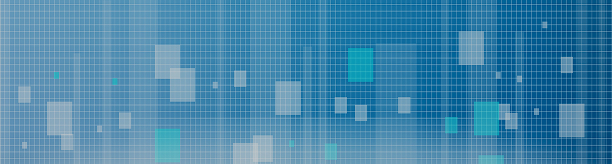- share :
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、もはや大企業だけでなく、中小企業にとっても喫緊の課題です。しかし、日本のDXの現状をみると、多くの中小企業がDXを「コスト削減」や「業務効率化」といった守りの側面でのみ捉え、その潜在能力を十分に引き出せていないようです。
大企業がDXを積極的に推進し、新たな市場を切り拓いている中で、中小企業が守りのDXにしか取り組まない状況が続けば、一気に競争力を失ってしまいかねません。
今こそ、中小企業はDXを「攻め」の戦略へと転換すべきなのです。
本記事では、中小企業がDXを「攻め」の戦略として捉え、持続的な成長を実現するための戦略を、具体的な事例と共に解説します。
DXの二つの側面:「守り」と「攻め」

DXには大きく分けて二つの側面が存在します。
一つは「守りのDX」です。これは、既存のビジネスモデルや業務プロセスをデジタル技術によって効率化し、コスト削減や生産性向上、リスク管理などを実現するものです。
例えば、クラウドサービスの導入によるITコスト削減や、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による業務自動化などが挙げられます。
もう一つは「攻めのDX」です。これは、デジタル技術を活用して新たな製品やサービス、ビジネスモデルを創出し、顧客体験を向上させ、競争優位性を確立するものです。
例えば、ECサイト開設による販路拡大や、AIを活用した顧客分析によるマーケティング最適化などが挙げられます。
DXを成功させるためには、「守り」と「攻め」の両輪をバランス良く推進することが重要です。「守り」のDXによって業務基盤を強化し、「攻め」のDXによって新たな価値を創造することで、企業は持続的な成長を遂げることができるでしょう。
大和ハウス工業の事例:建設DXを「攻め」に転換
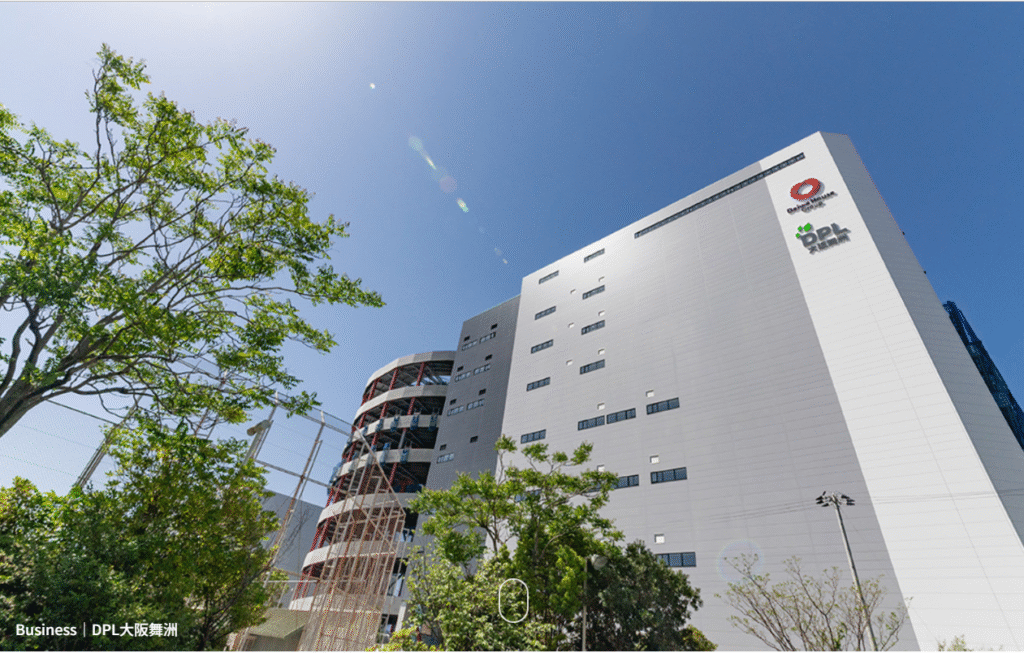
建設業界におけるDXのリーディングカンパニーである大和ハウス工業は、DXを単なる効率化ツールとしてではなく、事業戦略の中核に据え、新たな価値創造と持続的な成長を実現しています。
同社が「攻め」のDXで実現していることを、具体的な取り組みを通して見ていきましょう。
BIMデータを核としたデータドリブンな事業計画
大和ハウス工業は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)データを積極的に活用しています。BIMを使って、設計や施工の効率化をすると同時に、事業戦略の基礎となるデータとしても利用することで、徹底的にデータに基づく経営を実現しています。
- 設計段階でのシミュレーション:BIMデータを用いることで、設計段階で建物のライフサイクル全体をシミュレーションできる。これにより、工事期間だけでなく、維持管理コストやエネルギー効率なども予測し、顧客に最適な提案を行うことが可能となる
- サプライチェーンの最適化:BIMデータをサプライチェーン全体で共有することで、資材調達や生産計画を最適化し、コスト削減やリードタイム短縮を実現している
- 都市計画への活用:複数の建物データを統合し、都市全体のシミュレーションを行うことで、より高度な都市計画やスマートシティの実現に向けた取り組みを加速させている
顧客体験の向上と新たな価値創造
大和ハウス工業は、DXを通じて顧客体験を向上させ、新たな価値を創造しています。
- 顧客ニーズの可視化:顧客データやセンサーデータ(IoT機器を通じて取得される、顧客の行動や建物の利用状況に関するデータ)を分析することで、顧客のニーズや行動パターンを可視化し、よりパーソナライズされたサービスを提供する
- プレハブ建築とDXの掛け合わせ:プレハブ建築業界は、もともと規格化や工業化を追求する風土が根付いているが、この特性にDXを組み合わせることで、デジタル化された設計情報に数量や資材の単価情報を統合し、積算や見積もりをスムーズにするだけでなく、工程データも一元管理することで、現場のプロジェクトマネジメントを刷新した
- 維持管理サービスの高度化:IoTセンサーやAIを活用することで、建物の劣化状況や設備稼働状況をリアルタイムに把握できる仕組みを構築し、予防保全や遠隔監視などの高度な維持管理サービスを提供する
- 新規事業の創出:蓄積したデータを活用し、介護施設運営やエネルギーマネジメントなど、新たな事業領域に進出
デジタルループによる持続的な改善
大和ハウス工業は、設計、製造、施工、維持管理の各段階で得られたデータを蓄積し、それを再び設計にフィードバックする「デジタルループ」を構築しています。これにより、継続的な改善を可能にしました。
- 施工データの設計への反映:施工現場で得られたデータを分析することで、設計の課題や改善点を洗い出し、次の物件の設計に反映させている
- 顧客の声の製品開発への活用:顧客から寄せられたフィードバックや要望をデータとして蓄積し、製品開発やサービス改善に活用している
これらの取り組みにより、大和ハウス工業は建設業界におけるDXのリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。
同社の事例は、DXが単なるコスト削減ではなく、新たなビジネスチャンス創出や顧客満足度向上に繋がることを明確に示しています。
中小企業が「攻めのDX」を実現するためのステップ

では、大和ハウス工業という大手企業のDX事例から得た学びを中小企業が活かすためにはどのようにすれば良いのでしょうか?「攻めのDX」を実現するためには、以下のステップを踏むことが重要です。
自社の強みと市場機会を分析する
まず、自社の強みや独自性を徹底的に分析し、他社との差別化ポイントを明確にします。次に、市場のトレンドや顧客ニーズを調査し、潜在的なビジネスチャンスを見つけ出します。
この分析を通じて、自社がどの領域でDXを推進すべきか、具体的な方向性を定めることができるのです。リソースが限られている中小企業の場合は、広く浅く色々な分野に手を出すのではなく、自社の強みを最大限に活かして、攻めるポイントを見極めることが大切です。
市場調査においては、競合の動向も把握し、自社の立ち位置を客観的に評価することが重要となります。
顧客ニーズに基づいたデジタルサービスの開発
市場分析で得られた顧客ニーズに基づき、デジタル技術を活用した新たなサービスや製品を開発します。このとき、顧客の課題を解決し、利便性を向上させるような、付加価値の高いサービスを提供することが重要です。
開発プロセスでは、顧客からのフィードバックを積極的に取り入れ、ニーズとのギャップを埋めていきます。プロトタイプを作成し、テストを繰り返すことで、より完成度の高いサービスを目指しましょう。
データ活用による顧客体験のパーソナライズ
顧客データを収集・分析し、顧客一人ひとりに合わせた最適な情報やサービスを提供します。顧客の属性、購買履歴、行動履歴などのデータを活用することで、顧客の嗜好やニーズを把握し、個別のニーズに対応できるでしょう。
例えば、ECサイトであれば、顧客の閲覧履歴や購買履歴に基づいて、おすすめ商品を提案したり、パーソナライズされたクーポンを提供したりすることが可能です。
外部パートナーとの連携によるエコシステム構築
自社のリソースだけでは難しい場合、外部の専門企業やスタートアップと連携し、新たな価値を共創します。異なる強みを持つ企業と連携することで、より高度なサービスやソリューションを提供できるのです。
例えば、AI技術を持つスタートアップと連携して、顧客分析やマーケティングを強化したり、IoT技術を持つ企業と連携して、新たな製品やサービスを開発したりすることが考えられます。中小企業が内部のリソースだけでDXを進めていくことは、時として困難なものです。外部パートナーとの連携が成否を分けるカギになる場合も少なくありません。
人材育成と組織文化変革
攻めのDXを進めていくためには、社内での人材育成と組織文化の変革を目指すことも重要です。DXを推進できる人材を育成し、変化を恐れずに挑戦する組織文化を醸成します。従業員に対するデジタルスキル研修やDXに関する意識啓発を行い、全社的なDX推進体制を構築しましょう。
また、失敗を恐れずに挑戦できる組織文化を醸成し、従業員のアイデアや意見を積極的に取り入れることが欠かせません。経営層がリーダーシップを発揮し、DX推進を牽引することで、組織全体の変革を加速させることができます。

執筆者
株式会社MU 代表取締役社長
山田 元樹
社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。