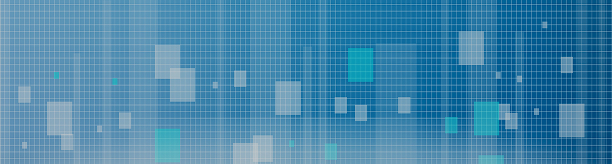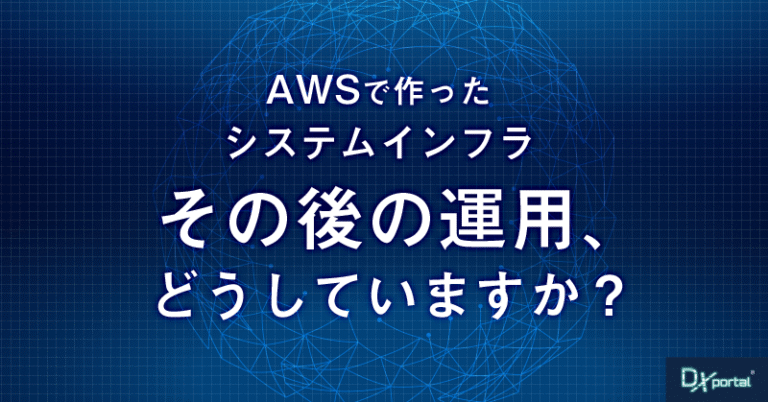
- share :
AWS(アマゾンウェブサービス)やAzure(アジュール)、GCP(グーグルクラウドプラットフォーム)などのクラウドサービスの進化は、インフラ構築のハードルを格段に下げ、中小企業でも迅速なシステム導入を可能にしました。
しかし、インフラが「簡単に構築できる」ようになったことで、逆にその後の運用の難しさが浮き彫りになっています。
実際、システムトラブルが発生した際に「エラーは出ているが、多岐にわたるログの中から何が原因か分からない」という問題。あるいは、「担当者が変わると過去の知見が活かせず、対応ができない」といった運用が属人化する課題にも直面している企業は多いのではないでしょうか。
本記事では、この「構築の容易さ」と「運用の複雑さ」のギャップに焦点を当て、特に中小企業が抱えるクラウド運用特有の課題を論理的に解説します。具体的には、システムトラブル時の原因特定が困難な構造、ノウハウがブラックボックス化する現状を明らかにします。
さらに、これらの課題を解決する現代の運用管理製品が提供する「見える化」と「判断支援」の具体的な価値と、その導入ステップに加え、クラウド導入後の安定運用を目指し、貴社のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進における意思決定を支援する情報をお届けします。
アラートが教えてくれない「エラーの本質」

クラウド環境では、システムが何らかの異常を検知すると、監視ツールやクラウドサービス(例:AWS CloudWatch)が、以下のようなアラートを発します。
- EC2インスタンスが異常終了した
- RDSの接続エラーが発生した
- Lambda関数がタイムアウトした
- CPU使用率が急上昇した
こうしたアラートは、確かに「何かが起きている」という事態を運用担当者に知らせてくれます。しかし、アラート自体はあくまで「異常が発生した事実」を告げるスタート地点に過ぎません。「何が真の原因なのか」「どう対処すれば復旧できるのか」という、運用で最も肝心な判断までは教えてくれないのが現実です。
このアラートと真の原因特定との間に存在するギャップこそが、クラウド運用における時間とコストを増大させる要因となるため、その具体的な実態を解説します。
ログの「量」と「複雑性」が原因特定を困難にする
実際の運用現場では、エラーが発生すると、まず詳細を知るためにログを確認します。しかし、分散型のクラウドシステムはサービスごとにログが出力されるため、その量は数千行、数万行に及ぶことが一般的です。
膨大なログの中から、担当者が目視で原因となる特定の箇所を探し出す作業は、多大な時間と労力を要するでしょう。その結果、ログをなんとなく眺めるだけに終わってしまい、根本的な解決に繋がらず、対処療法で復旧を試みることになりかねません。
また、現代のシステムは、アプリケーション、データベース、ネットワーク、外部APIなど複数の要素が絡み合って動作しています。そのため、エラーが発生しても、アプリケーションの異常が原因なのか、それともデータベースの遅延が原因なのか、因果関係が不明瞭になるケースが散見されます。個別のログを眺めるだけでは関連性が見えず、問題解決に結びつかない時間が過ぎていくだけなのです。
過去のノウハウが活かせない運用現場の課題
もう一つの深刻な問題が「属人化」です。過去に同様のエラーが発生し、特定の担当者の知識や経験で解決したとしても、その「対応手順」や「知見」が社内で体系的に記録・共有されていないことは、多くの企業に共通する課題でしょう。
その担当者が退職したり、異動したりした場合、残されたメンバーは過去の対応履歴を辿れず、トラブルが発生するたびにゼロから原因調査と対応を始めざるを得ない状況に陥ります。これは、システム停止時間を長引かせ、企業の信用失墜や機会損失に直結する大きなリスクになるのです。
クラウド運用の課題を解決する「運用管理製品の機能」

前章で解説した通り、クラウド環境の運用では、複雑なログによる原因特定の困難さや、ノウハウが特定の担当者に集中する属人化といった課題が表面化しています。これらの課題は、システム停止時間の増加や運用コストの上昇に直結します。
本章では、こうした課題を克服するために、現在の運用管理製品が具体的にどのような機能を提供し、中小企業の安定運用を支援するのかを解説します。
運用管理製品が提供する「判断支援」の価値
システム運用で生じる「原因特定が困難」「ノウハウが属人化する」といった課題は、運用担当者の判断の迷いから生じています。現代の運用管理製品は、この判断をサポートする具体的な機能を提供することで、システムトラブルの解決までの時間を短縮し、担当者の負担を軽減することを目的としています。
単なる監視ツールに留まらず、運用管理製品は、「複雑な原因を特定する機能」と「ノウハウを自動で共有する機能」によって、クラウド環境の安定運用を力強く支援します。
複雑な原因を特定する「ログ自動分析」機能
複雑な原因調査を支援する「ログ分析」機能。システムトラブルの際、原因特定を難しくしていたのは、膨大なログの量と複数サービスが絡み合う複雑性でした。
ログはシステムの「健康診断書」のようなもので、そこにすべてのヒントが詰まっています。しかし、人間が目視で追うには限界があります。
そこで、運用管理製品では、AIやルールベースの仕組みを活用し、ログの中から「異常の兆候」や「関連イベント」を抽出・整理することで、調査の効率化を支援します。完全な自動原因特定ではありませんが、調査の方向性を早期に示すことで、復旧までの時間を短縮できます。
- 関連ログの抽出と整理:エラー発生時に、複数サービスに散在するログから、問題の引き金となったイベントや連鎖事象を選び出し、時系列で整理。これにより、どのサービスで最初に異常が起きたかを「見える化」する
- 原因候補の提示:過去の障害パターンや構成変更履歴と照合し、「このエラーは昨日の設定変更が影響している可能性があります」「DB接続エラーが頻発しているためネットワーク遅延が疑われます」といった調査のヒントを提供。手探り状態を回避し、調査の初動を加速する
ノウハウを自動で共有する「属人化解消」機能
「このエラーが出たらどう対応すべきか」というノウハウが特定の担当者に集中し、社内で共有されない「属人化」は、運用管理製品によって解消できます。
- 対応ガイドの表示:過去のトラブル対応時に担当者が行った操作や、最終的な復旧策をシステムが自動的に記録し、新たなエラー発生時に「このエラーは過去に◯◯の再起動で復旧した事例があります」といった具体的な対応のヒントを表示する。これにより、経験の浅い担当者でも、迷うことなく初動対応が可能となる
- 構成変更履歴の自動記録:誰が、いつ、どの設定を変更したかを自動で記録し、障害発生との関連性を分析する。システムの柔軟な設定が可能なクラウド環境では、担当者ごとの設定変更がトラブルの原因となるケースがあるが、この機能により「変更内容」と「障害の発生」の因果関係を客観的に把握しやすくなる
アラートは「スタート地点」、原因分析は「運用管理製品の仕事」
「エラーが出た」だけでは、運用は始まりません。本当に必要なのは、「なぜそのエラーが出たのか」「どう対応すればいいのか」という判断支援です。
今の運用管理製品は、ログの自動分析、原因候補の提示、対応ガイドの表示などを通じて、運用担当者の「迷い」を減らし、迅速かつ的確な対応を可能にします。この自動化された分析機能こそが、クラウド時代における運用業務の本質であり、企業のDX推進を陰で支える要素となるのです。
まとめ:クラウド時代の運用は「見える化」と「判断支援」が鍵
クラウドサービスによるDX推進は、企業に俊敏性をもたらしますが、「構築の容易さ」とは裏腹に、運用の複雑さが増しているのが現状です。特に中小企業において、システム障害時の原因特定や、対応ノウハウの属人化は、事業継続における大きなリスクとなり得ます。
本記事では、アラートだけでは分からない「エラーの本質」を解説し、この課題を克服する具体的な手段として、運用管理製品が果たす役割を論理的に示しました。
現代の運用管理製品は、ログの自動分析や対応ガイドの表示といった「見える化」と「判断支援」の機能を提供します。これにより、経験や勘に頼りがちだった運用業務を標準化し、誰でも安心してクラウドシステムを運用できる体制を構築することが可能です。
「クラウド構築は完了したが、その後の運用体制に不安がある」
「トラブル対応が属人化しており、業務負荷の軽減を進めたい」
そうお考えの方は、アラートはスタート地点に過ぎず、原因分析は運用管理製品の仕事であるという視点に立ち、最新の運用管理ツールがどこまで貴社の運用課題を解決できるのか、その可能性を検討してみてください。貴社のクラウド環境を、より安全に、そして効率的に運用できる環境が整うはずです。

執筆者
株式会社MU 営業部
帯邉 昇
新卒で日本アイ・ビー・エム株式会社入社。ソフトウェア事業部でLotus Notesや運用管理製品Tivoliなどの製品担当営業として活動。その後インフォテリア株式会社、マイクロソフト株式会社で要職を歴任した。キャリア30年のほとんどを事業立ち上げ期のパートナーセールスとして過ごし、専門はグループウェアやUC、MA、SFA、BIなどの情報系で、いわゆるDXの分野を得意とする。(所属元)株式会社エイ・シームジャパン。