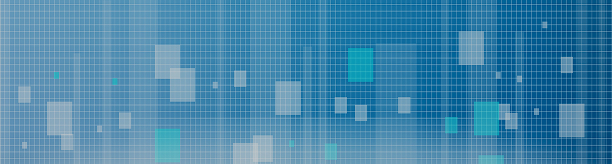- share :
デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みは年々進んでいますが、この数年でその本質から変わりつつあります。従来のDXで「業務効率化」に終始していた取り組みのあり方はすでに過去のものとなり、AIの進化によって、「労働力の概念が根本から覆り、富の構造が激変する」という、極めて確度の高い未来予測が、今、企業に突きつけられている状況です。
この変化は、労働力のあり方、企業の存続、そして私たちの未来そのものに根本的な問いを突きつけ、危機的な状況への転換を迫るものだと言ってよいでしょう。
本記事では、エンジェル投資家として活動し、スタートアップ支援やアントレプレナーシップ教育に携わる、株式会社tsam代表取締役の池森裕毅氏に、AI時代におけるDXの本質と、中小企業の経営者が持つべき「覚悟とスピード」について伺いました。
AIによって引き起こされる産業構造の激変は、リソースの限られた中小企業にとっては「絶望」的な未来を予感させるかもしれません。ですが、今すぐ行動を起こすことで、「希望」に変える道筋も残されています。貴社がこの大きな変化の波にどう向き合い、生き残っていくべきかを考えるための指針を、池森氏の言葉から感じ取ってください。
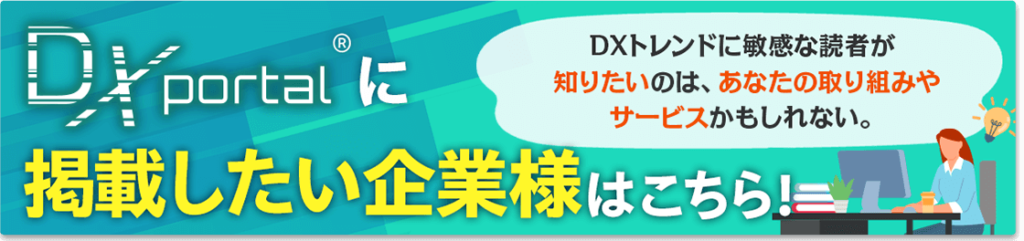
DXの潮流は「AI以前」と「AI以降」で明確に分断された
DXという概念は、ここ最近で明確に一段階変わったと池森氏は指摘します。その起点が、AIの存在です。従来のDXで満足している企業は、すでに「AI以前」の旧体制になってしまっており、淘汰の波にさらされ始めてる、と池森氏は語ります。
池森氏

「DXは、この1年で明確に一段階変わったと言えます。これまでのDXは、SaaSなどのツール導入で業務効率化を進めることが主な目的でした。しかし、ChatGPTなどの生成AIが世に放たれて以降、最近ではAIエージェント(自律的に複数のタスクを実行し、複雑な業務を自動化できるAIシステム)の活用が次の段階として必須になっています。
AIエージェントの出現によって、今までデジタル化や効率化を諦めていた部分や、人手による作業が必要だったルーティンワークの多くが、自動化されることになりました。
実際、ある程度DXが進んでいた企業も、さらにAIを使って自動化するという「DXにブースト」をかけるのが今の流れです。だからこそ、現状でAIを使いこなしている企業とそうでない企業の間では、すでに差が激しくなり、その差が埋まらない状況になりつつあると考えます。」
DX推進に乗り遅れた企業に残された「二つのチャンス」
DX推進に取り組んでいない、あるいは取り組んではいても限定的なデジタル化に留まっている企業は、日本中にまだまだたくさん存在します。
AIの波は、すでにDXに取り組んでいる企業にとっては、さらなる効率化のブーストができる「希望」に見えます 。しかし、DXに乗り遅れた上にAIの活用もしていない企業にとっては、この技術革新が格差を決定的に広げる「絶望」に見えるかもしれません 。
しかし、この状況に対して池森氏は、むしろ「チャンス」として捉えるべきだと語ってくれました 。
池森氏
「例えば、従来のDXでは、手書きの書類をデータ化するために、まずOCR(光学文字認識)システムを導入し、次にフォーマットを統一するための整備を行い、最後に基幹システムに連携させるという、時間とコストのかかる複数のステップが必要でした。
おまけに、取引先ごと、あるいは部署・部門ごとにフォーマットが違うなどの問題もあり、こうしたステップを踏んだとしても統一したデータ化が難しかったという場合もあったでしょう。
しかし、AIであればどんな手書きの文字でも読み取り、バラバラなフォーマットも自動で構造化・統合し、そのままデータとして活用することができます。これにより、煩雑な中間工程をスキップし、一気に業務に組み込むことが可能になるのです。これは、デジタル化の『面倒くさい部分』を一気に解決し、DXを加速させる強力な追い風となるはずです。
これまでDXができていなかった企業でも、AIの力を借りて一気にリープフロッグ(カエルが跳ぶように、従来段階を飛び越えて一気に発展する現象)ができる可能性があるのが『今』なのだと言えるでしょう。」
リープフロッグという言葉が示す通り、今からでも「AIを使ってDXを進める」という選択をすれば、遅れを取り戻すことは不可能ではないというのは、未だDXにうまく取り組めていない企業に大きな勇気を与えてくれる言葉ではないでしょうか。
10年後の未来予測:労働力不足はAIとヒューマノイドで解消される
AI活用によって業務を一気に効率化できるとしても、現在の多くの企業が直面している労働者不足は今後もさらに深刻化していくと言われています。この根本的な課題を解決しない限り、人材確保が難しい企業が未来に「希望」を見出すことは難しいように思われます。そんな疑問を池森氏に投げかけてみたところ、驚くべき回答が返ってきました。
池森氏

「現在社会問題となっている人材不足は、今後10〜15年の一過性の問題に過ぎません。私は、最終的には、『世界中で労働力不足は解消される』という予測を立てています。その根拠は、AIとヒューマノイド(人型ロボット)による労働力の代替が進むためです。
オンラインの仕事はAIに、リアルの仕事はヒューマノイドに代替されます。まず、オンラインで経済的価値がある行為のほとんどは、今後3年以内にAIに取って代わられるでしょう。さらに、美容師や料理人、介護・福祉などのリアルな仕事も、10年後にはヒューマノイドが代替する未来が現実のものとなりつつあります。将来的には、人材が不足するのではなく、人間がやる仕事がないという状況になる可能性が高いとすら言えるのです。」
労働から資本へ:富の拡大が格差を生む「絶望的な未来」
AIとヒューマノイドが労働市場を根本から変革する未来は、富の集中がさらに加速し、「資本家(オーナー)」と「プロレタリアート(労働者)」の格差が拡大する「絶望的な時代」になる可能性を秘めていると池森氏は警鐘を鳴らします。
池森氏
「ヒューマノイドを導入することで、オーナー経営者は、従来労働者に支払っていた給与や社会保険の費用を支払う必要がなくなります。つまり、そうした「従業員に払っていた経費」を全て吸収することになり、富の集中がさらに進むのです。
例えば、今まで美容師を5人雇って経営していたオーナーは、5人に給与と社会保険を払っていました。しかし、今後5人の労働者をすべて解雇し、ヒューマノイド5体を導入すれば、人間に払っていた給与や社会保険の費用を一切支払う必要がなくなります。その分の費用はすべてオーナーに吸収されるのです。そして、これは美容師だけでなく、介護、福祉、看護、料理など、作業のパターン化や標準化ができる部分が大きい市場で起こります
一方で、人間が担う仕事は、AIやヒューマノイドがやる価値もない、市場規模が小さく面倒な領域にしか残されません。そこに労働者が集中することで価格競争(ダンプ)が起き、さらに賃金が買い叩かれるという未来が待っているでしょう。これは、プロレタリアート(労働者階級)にとっては絶望的な未来であり、すでにアメリカでは若年層の失業率が跳び抜けて高くなっているように、AIによる代替が始まっています。
こうしたAIとヒューマノイドが労働市場を根本から変革する未来は、フランスの経済学者トマ・ピケティ氏が提唱した『R>G(資本収益率が経済成長率を上回る)』という格差拡大の構図を、さらに加速させるものとなります。この変革は、富の集中が加速し、『資本家(オーナー)』と『プロレタリアート』の格差を拡大させる『絶望的な時代』になる可能性を秘めているということです。」
この予測は、企業経営者に「労働力に依存しない経営戦略」への転換を、そしてDXを加速させることを強く迫るものと言えるでしょう。同時に労働者としては、「持たざるもの」になってしまう前に、自身の持つ労働力を資本に転換する意識を明確に持つ必要があります。
市場の可能性と「時価総額100億円」の壁
AIとヒューマノイドが労働市場を破壊し、多くの労働者が仕事を失うかもしれない。企業にとっても生き残るためには「労働力に依存しない経営戦略」への転換を迫られている。この予測は、労働者にはもちろんですが、企業経営者にとってもショッキングな話でしょう。
では、この激変する時代において、企業が生き残り、富を生み出す「資本側」に回るためには、具体的にどのような戦略と視点を持つべきなのでしょうか。
AI時代において、企業が生き残り、投資家に選ばれるために必要なのは、プロダクトの優秀さよりも、経営者自身の「リテラシー」と「市場の可能性」に対する深い洞察力だと池森氏は語ります。では、投資家目線として考えると、魅力的な企業とはどのような条件を持っているのでしょうか?
池森氏

「上場基準の厳格化を一つの背景に、我々投資家は、そのビジネスが将来的に時価総額100億円をつけられるポテンシャル(市場規模)があるかどうかを重視しています。つまり、DXを進める際にも、目先の効率化や小さな課題解決だけでなく、『その先にどのような巨大な市場があるのか』という、潜在的な需要の視点を持つことが重要となります。そちらのほうが、プロダクトの完成度や魅力よりも遥かに重要です。」
この視点こそ、自社のプロダクトやDX戦略が、単なる社内改善に留まらず、広大な市場を捉える可能性があるかを測る、重要な評価基準となるでしょう。

執筆者
DXportal編集長
町田 英伸
自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。