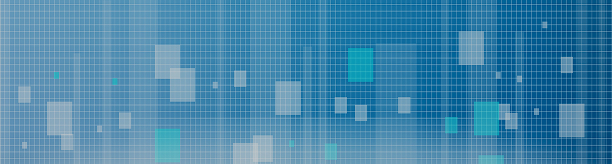アサヒの教訓から学ぶDXの「影」:サイバー攻撃の深刻な現実

これまで見てきたとおり、DXがもたらす「光」の裏側には、事業の存続に関わる「影」も潜んでいます。今回アサヒが受けたサイバー攻撃はその象徴的なものだと言えるでしょう。
この章では、大企業アサヒを襲った攻撃事例を改めて掘り下げます。ここで強調したいのは、デジタル社会に潜む新たな脅威である「自社が見過ごしてしまったセキュリティリスクがきっかけで、取引先にまで損害を与えてしまう」という極めて切実なリスク構造です。
アサヒを襲ったサイバー攻撃の教訓
繰り返しになりますが、アサヒのランサムウェア被害は、デジタル化の進行がもたらす恩恵と表裏一体で、甚大な被害が発生する現実を突きつけました。同時期にアスクルでもランサムウェアによってシステム障害が発生したことから見ても、これはアサヒだけの個別的な問題ではなく、現代社会が抱える構造的な問題です。
これらの攻撃は、企業の根幹を成す受発注や物流システムを停止させ、業務麻痺という直接的な損害をもたらし、その結果、その取引企業、ひいては消費者にまで影響を与えるのです。
こうした攻撃の手口は巧妙化しています。攻撃側は、標的企業のシステムに侵入した後、すぐには攻撃に移らず潜伏し、管理権限の奪取や脅迫に使う個人情報の窃取など、綿密な準備を重ねます。さらに、サイバー犯罪組織が標的企業の財務状況まで事前に調査し、身代金の要求額を最大化する戦略を取っていることも確認されています。
残念ながら、デジタルの利便性を維持しながら、こうしたサイバー攻撃を完璧に防ぐことは現時点の技術ではほとんど不可能です。また、当然ながら、今回のアサヒのランサムウェア被害を防ぐために、その取引先である飲食店側ができたことはなかったと考えられます。それにもかかわらず、大企業が受ける攻撃の影響が、自店舗の「仕入れ停止」や「予約システム停止」という形で回り回って及んできてしまうのです。
間接的に被害を受けるリスクをゼロにはできないとはいえ、まずはこの構造を理解することが、自店舗の防御策を考える上では重要です。例えば、一つの取引先やシステムに依存しない仕入れ、営業に欠かせない商材の在庫数の検討、緊急時に助け合える同業との関係構築など、構造的なリスクを認識することで新たに見えてくる道もあるはずです。
飲食店が直面する「加害」リスク:取引先の信頼を破壊するサプライチェーン攻撃
今回のアサヒの事件をきっかけに、デジタル化したサプライチェーンの「影」の部分に注目が集まっています。ですが、飲食店DXアドバイザーの視点からすると、見逃されている論点があると感じています。それが、「加害者」になるリスクです。
どんなに小規模な飲食店でも、取引先を持つ限り、サイバー攻撃の「踏み台」となり、間接的に「加害者」となってしまうリスクから逃れられない現実を直視しなければならないと考えています。
サイバー攻撃の鉄則はもっともセキュリティが手薄な穴を探すことにあります。ランサムウェアにおいても、セキュリティが手薄な中小企業を最初の侵入経路として利用し、そこから繋がっている取引先の大企業(例えば、大手食材卸や決済プラットフォーム)を狙うという手口が主流です。従業員のパソコンに届いた一通のウイルスメールが、知らず知らずのうちに取引先のシステムに侵入する足がかりを与えてしまうのです(参考:IPAプレスリリース)。
もちろんサイバー攻撃の「踏み台」にされた企業に一切悪意はありません。しかし、攻撃された側から見れば、自社に甚大な被害をもたらした「加害者」のように捉えられても仕方ないのではないでしょうか。
自店舗からのウイルス感染が、取引先のシステム停止への攻撃を引き起こした場合、その損害は一企業では到底負いきれないものになる可能性もあります。法的な補償責任の有無は別にしても、重要な取引先を失うようなことになれば、事業継続の根幹をも破壊する事態へと発展しかねません。
ウイルスの侵入経路と「人の弱点」が露呈する飲食店のリスク構造
サイバー攻撃と聞くと、高度なハッキング技術を想像しがちですが、実際は極めて単純なミスから始まることが大半です。攻撃は、フィッシングメールや不審なサイトといった、人の操作ミスを介して行われます(参考:国内サイバーリスクラウンドアップ2025年上半期を公開/トレンドマイクロ公式サイト)
飲食店のリスク構造において、この「人の弱点」はさらに拡大します。飲食業界特有の従業員の流動性や、日々の業務に追われることによるセキュリティ教育機会の不足が、大きな課題です。
最新のセキュリティソフトを導入しても、従業員が誤ってウイルスが仕込まれたファイルを開いてしまえば、その防御は簡単に無力化されます。この「人」が抱える脆弱性が、セキュリティ対策における最大のボトルネックになっている構造を理解し、対処することが必須であると言えるでしょう。
デジタル時代の危機管理:光を活かすための「守りの基盤」

DXの「光」を最大限に活かし、同時に「影」を遠ざけるためには、強固な「守りの基盤」が不可欠です。
この章では、適切なセキュリティ対策を講じるためのマインドセットとそのための方法について取り上げます。
セキュリティ対策は命を守る「保険」
セキュリティ対策は、売上を生まない単なるコストと見なされがちです。確かに、日常生活の中ではセキュリティ対策の効果は見えにくいため、ただコストだけがかさんでいるように見えてしまうかもしれません。
しかし、この認識は改める必要があります。セキュリティ対策は、サイバー攻撃によって甚大な損害を被るリスクを回避するための事業を守り抜くための保険であり、デジタル時代における必須の投資です。これは、車を運転するなら自動車保険に加入しなければならないように、自分だけではなく、相手を守るための者でもあるのです。
飲食店の場合では、お客様が安心して予約をし、決済を行い、食事を楽しんでいただくための重要な基盤の一つがセキュリティにあたるといえます。また、取引先に安心して取引を続けてもらうための約束ということもできるでしょう。
飲食店経営者が持つべき「最悪を想定する」マインドセット
アサヒやアスクル、KADOKAWAの事例が示すように、どのような企業のシステムであっても100%安全ではありません。今回のようなサイバー攻撃だけでなく、自然災害や予想外の倒産などにより急にシステムが停止する可能性は常に存在します。不確実性、予想不可能性が増す現代において、事業を継続するためには、「最悪を想定する」マインドセットがますます重要になっています。
このマインドセットの重要性を端的に表してるのが、サイバーセキュリティの世界的なリーダーであるトレンドマイクロの担当者の「サイバー攻撃は『もし起きたら』ではなく、『起きる前提』で対策を進める必要がある」という言葉です。サイバー攻撃を受けた際の被害が、平均10.2日にも及ぶ現実を直視して、予め備えておくことが求められます。これは、BCP(事業継続計画)の考え方を取り入れることを意味します。
具体的には、POSや予約システムが数日~数週間使えなくなったときのことを想定して「一時的に紙の注文票で営業する」、「復旧まで電話予約に切り替える」といった手動での営業手順を事前に定めておくことが考えられます。
また、システムが完全に破壊された場合の最後の砦として、データの安全なバックアップを取ることは不可欠です。「最悪を想定する」という視点に立てば、顧客データや会計データは、店舗内のシステムとは完全に切り離された場所(安全性の高いクラウドサービスなど)に二重に保存する仕組みが必須となるでしょう。
外部専門家の活用と初期防御の構造化
「人」という脆弱性がある以上、100%攻撃を防ぐことはできませんが、それでも攻撃者の手口の巧妙化に対応して、様々なセキュリティ対策が生み出されています。ですが、中小企業が最新のサイバー攻撃の手口や防御策を自力で追い続けることは極めて困難です。最新の状態を保つためには、信頼できるITサポートや外部専門家に相談し、セキュリティ診断を受けることが重要です。
外部の視点を入れることで、自店舗の脆弱性や、フィッシングメール対策といった「人」の教育の課題を客観的に把握し、最も費用対効果の高い初期防御を実現できます。セキュリティ対策は、個人の努力に任せるのではなく、外部の知見を借りて組織全体でカバーする基盤を構築することで、その効果を最大化できるのです。
まとめ:安全なDXこそ、未来の「おもてなし」である
DXは、私たち飲食店にとって新しい価値を創出する不可欠な「光」ですが、アサヒの事例が示すように、一瞬で事業継続の根幹を奪う「影」とも隣り合わせです。私たちは、その「被害者」にも、場合によっては取引先に損害を与える「加害者」にもなってしまうリスクを常に抱えています。
そのため、そのリスクを最小化するためのセキュリティ対策は、もはや後回しにできる要素ではなく、お客様のかけがえのない情報と、取引先の信頼を守り抜く、デジタル時代の最前線です。
アサヒのランサムウェア被害を一つのきっかけに、自店舗のセキュリティを見直してください。
具体的な対策の計画や、中小企業の現状に即したセキュリティソリューションについてご相談が必要な場合は、DX推進の全体像を理解し、課題に寄り添える専門的な知見を持つ当メディア運営会社へご連絡いただくことが、最も安全なDXへの近道となるでしょう。

執筆者
DXportal編集長
町田 英伸
自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。