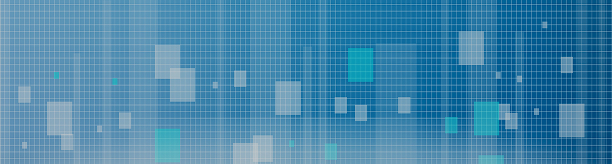- share :
生成AIを巡る覇権争いが、世界のビジネスシーンを揺るがしています。
その最前線を走るGoogleやAmazonなどの米ビッグテックは、2025年に総額50兆円規模のAI関連設備投資を計画しており、各社が覇権を握るために巨額の資金投入予定を表明しました。これは2024年に比べ、各社とも3~4割増しの数字です。
一方で、米国の巨大資本との間には、依然として大きな隔たりがあるものの、中国のAIスタートアップDeepSeekが低コストで高性能なAIの開発に成功するなど、グローバルなレベルでの争いに発展しています。
この熾烈な競争の鍵を握るのは、単なる開発力だけではありません。「運用」と「GPU(画像処理装置)」という二つの要素が、勝敗を左右する重要なファクターとなります。
本記事では、米中それぞれの戦略の違いを分析し、その上で日本の中小企業がこの状況から何を学び、どのようにDX戦略に活かすべきかを考察します。
巨大な潮流の中で、中小企業が生き残るための道筋を、共に探求していきましょう。
生成AI開発競争から運用競争へ

生成AI技術の開発競争は、新たな局面を迎えています。初期の技術開発段階を経て、現在は実際のサービス運用へと焦点が移りつつあるのです。
AI技術を社会実装し、継続的に価値を提供するためには、開発段階をはるかに上回る資源と戦略が求められます。
例えば、生成AIの代表格であるChatGPTは、ユーザーからの多様な質問に対して、高度な自然言語処理技術を用いて応答することで知られています。この技術が大きな注目を集めて、一気に利用者を獲得したわけですが、このサービスを維持するためには、膨大な計算資源(コンピューターの処理能力やメモリ、サーバーなどのこと)と、それを支えるインフラストラクチャーが不可欠です。
画像生成AIも同様に、高品質な画像を瞬時に生成するためには、サービスを開発・運用するための専門的な知識はもちろん、高性能なハードウェアとソフトウェアが求められます。
このように、生成AIの本格的な運用には、技術力だけでなく、それを支えるための大規模な設備投資と継続的な運用体制が不可欠なのです。
開発競争が激化する中で、生成AIサービスを提供している企業はどのようにしてこの「運用」という新たな課題に対応し、競争優位性を確立していくのでしょうか。本章では、生成AIの運用に焦点を当て、その現状と未来について考察していきます。
米国勢の戦略:大規模「運用」と「ユーザーエンゲージメント」の追求
米国勢は、潤沢な資金を背景に、生成AIの「運用」フェーズにおいて、圧倒的な優位性を確立しようとしています。当然ながら、企業によって戦略の細かい部分は異なるものの、いずれの企業も単に技術を提供するだけでなく、ユーザーを積極的に巻き込み、サービスへの深いエンゲージメントを築くことに重点を置く傾向があります。
例えば、OpenAIが1,400ドル/約21億円(推定)もかけてスーパーボウルでCMを放映した背景には、広範な視聴者に対してChatGPTの認知度を高め、新たなユーザー層を開拓する狙いがありました。さらに、ユーザーを獲得すると同時に、大規模データセンターへの巨額の投資を行い、AIサービスの安定稼働と高速処理を支えて、ユーザー体験を向上させるための基盤構築を狙っていたのです。
OpenAIは、アメリカで最も視聴率が高いといわれるイベントで宣伝をすることで一気に認知度を高め、その後の継続的なユーザーを獲得することに成功したと言ってよいでしょう。
Googleも似たような戦略を用いて、Geminiのユーザーを5億人まで増やそうとしています。多様なデバイスやプラットフォームを通じてGeminiへのアクセスを容易にすることで、日常生活やビジネスシーンでの利用を促進しようとしているのです。日常的にGeminiを使う機会を生み出し、ユーザーエンゲージメントを高めようとしているのです。
このように、米国勢は、技術力だけでなく、マーケティング戦略やユーザー体験の最適化を通じて、生成AI市場におけるリーダーシップを確立しようとしています。
中国勢の苦境:GPU制約と「運用コスト」の壁
中国勢は米国に対抗して生成AIに力をいれているものの、米国の制裁による高性能GPUの調達難という大きな課題に直面しています。DeepSeekが低コストでのAI開発に成功したことなど中国のAI技術を示すニュースがある一方で、大規模な運用に必要なGPUの不足がサービス展開におけるボトルネックになっているのです。
GPU不足は、単に計算資源の制約があるという点に留まらず、運用コストの増加にも繋がります。限られた資源を効率的に活用するためには、高度なソフトウェア技術が求められますが、それが新たなコストを生む可能性もあるでしょう。
中国勢は、この課題を乗り越えるためにソフトウェアの最適化やクラウドサービスの活用など、様々な手段を講じていますが、現時点では根本的な解決の目途は立っておらず、GPUの制約が、大規模なユーザー基盤を構築し、サービスをスケールさせる上での大きな障壁となっています。
このような状況を踏まえると、今後の中国勢は、技術革新によるGPU依存度の低減や、サプライチェーンの多様化を戦略のかなめに据えるしかないでしょう。
生成AIの未来は米国優位か?
これまで紹介してきた通り、現時点では、資金力とGPU調達力において優位に立つ米国勢が、生成AI市場を牽引しています。中国勢は、GPUの制約がサービス拡大を阻む要因になっています。しかし、中国勢も独自の技術力と市場戦略で巻き返しを図っており、今後の展開は不透明です。
生成AIの覇権争いは、技術開発だけでなく、運用戦略、ユーザーエンゲージメント、そして国際的な政治経済状況など、多岐にわたる要素が複雑に絡み合っています。
今後の技術革新や市場の変化によっては、勢力図が大きく塗り替えられる可能性も十分にあります。このまま米国が生成AIの覇権を握っていくのか、中国が巻き返してくるのか、それとも新たな新興勢力がその争いに加わるのかを予測することは困難です。
いずれにしても、この生成AIの覇権争いは、技術革新をさらに加速させ、より高度で多様な生成AIサービスを生み出す原動力となることは間違いありません。

執筆者
株式会社MU 代表取締役社長
山田 元樹
社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。