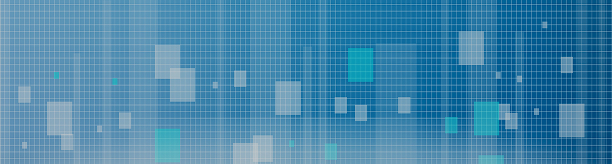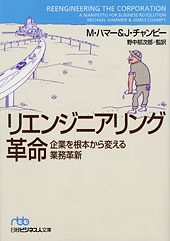テーマ4:AIが生み出した新たな「DX戦略」とは?
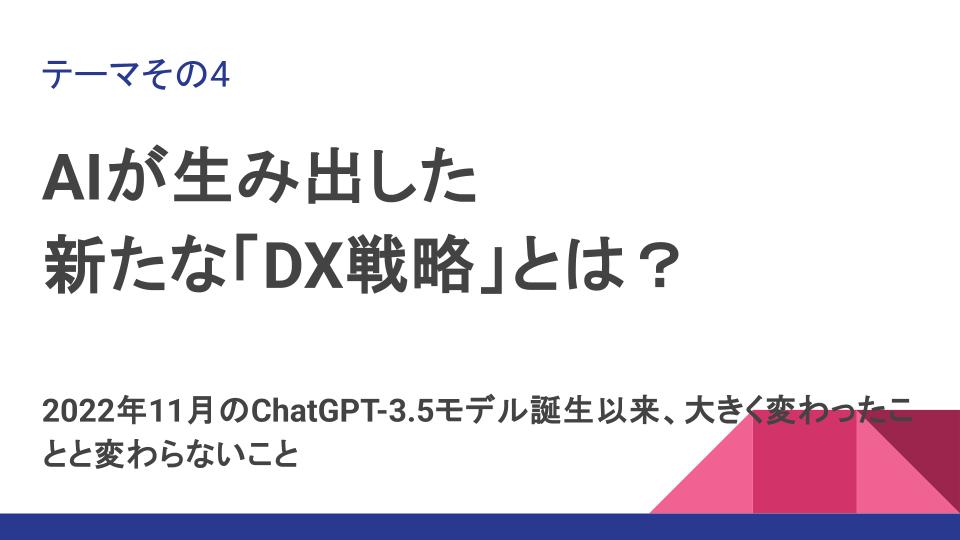
編集長
「最近のDXにおける生成AIの活用は無視できないトレンドです。ChatGPT-3.5の誕生に端を発する生成AIの進化は、DX戦略に影響を与えているでしょうか?また、与えているとしたら、それはどのような変化だとお考えですか?」
山田
「AIがあるからといって、人間の根源的な価値が変わるとは思っていません。AIは道具であり、それをどう使うかという人間の戦略自体は変わってきたかもしれませんが、根本的な『人間が何をやりたいか』という部分は変わらないでしょう。」

福田氏
「私も同意見です。ただし、AIは『道具』として非常に強力なものです。人間がアイデアを生み出すのに1週間かかっていたものが、AIを活用することでわずか数十分で実現できる事例も出てきています。AIは人間が考えつかなかったような新たな視点や組み合わせを提示してくれる、まさに変革を加速させる存在です。」
編集長
「AIは単なるツールであり、それを使いこなす人間の能力こそが問われる、ということですね。とはいえ便利なツールであるAIをうまく活用することによって、これまで見えなかったものが見えるようになる、ということでしょうか?」
福田氏
「まさにその通りです。AIにどんな情報を与えるか、どんなヒントを提示するか、という『プロンプト』や『種』となる部分は、やはり人間の判断が必要です。人間が創造してデジタルに与える情報がなければ、AIは動くことができません。そういう意味ではどれだけAIが進化しても、人間の役割はまだまだ大きいと感じています。」
山田
「AIによって効率化される仕事がある一方で、『この人のハンコがあれば大丈夫だ』というような、信頼感をベースとした目視確認など、人間が行う仕事が増える部分もあると思います。AIは、効率化だけでなく、信頼性や安全性を担保するための人間の役割をむしろ際立たせているのかもしれません。」
テーマ5:2030年へ向けたDXの未来予測
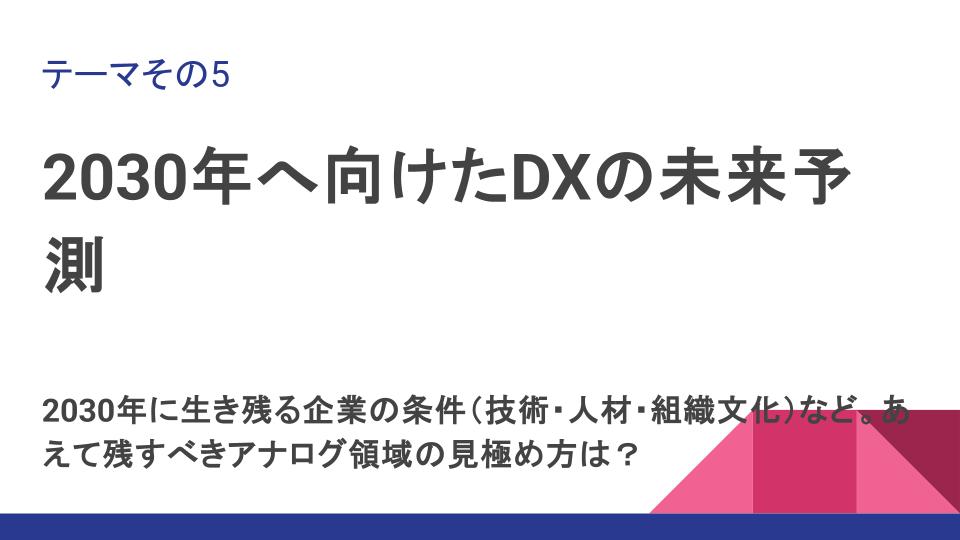
編集長
「最後に、これから5年後。2030年に生き残る企業の条件とは何でしょうか? また、あえて残すべきアナログ領域の見極め方についてもお聞かせください。」
福田氏
「約30年前にも『リエンジニアリング革命』という、今と似たような変革が提唱されていましたが、今は『DX(デジタルトランスフォーメーション)』という言葉になっています。ですので、時代とともに言葉は変わりますが、企業活動を変革するという本質的な流れは不変だと考えています。
もしかしたらこれから数年後に、『DX』という言葉は消えていくかもしれません。それでも、DXの先に『〇〇トランスフォーメーション』といった新たな言葉が生まれて、変革は続いていくはずです。
特に私は、これからは『エンゲージメント・トランスフォーメーション』とでもいうような概念が大きな鍵を握っているのでは?と感じています。エンゲージメントとは、元々は「婚約」「約束」などを意味する言葉で、ビジネスにおいては企業と従業員または企業と顧客との間の「深いつながり」や「関与」を指した言葉です。ですので、『従業員エンゲージメント経営』といえば、従業員が会社や組織に対して愛着を持ち、自発的に貢献したいと思える経営のことになります。
これを個人に置き換えれば、自分に対して自発的に自分を高める、つまり自己肯定感のようなものでしょうか。企業においても個人においても、そういったエンゲージメントを核とした変革が、今後はますます重要になってくると思います。」
編集長
「DXとは、デジタルによって組織の属人性を排して効率化を図るといった役割も持っていると思うのですが、これからはむしろそうした『人の想い』のようなものにフォーカスしたDXが重要となる、という意味では、まさにそこが残すべきアナログな部分ですね。」
山田
「2030年に向けては、宇宙や深海といった新たなリソースを含めたDXが広がる可能性もあります。その中で、企業も人も『自分の軸は何だろうか』という問いを突き詰め、必要なものを選び取る力が問われるのではないでしょうか。そこに対して、DXは、企業が自らの成長戦略や生き残りの戦略を定義するための道具として使えるはずです。」
編集長
「デジタル化が加速する社会において、私たち人間が大切にすべきアナログな領域は何でしょうか?」
山田
「最も残すべきは『人間の勘』だと思います。場の雰囲気を感じ取って、なんとなく『いける感じがする』あるいは、『嫌な予感がする』と感じるような、経験に基づく直感は、まだデジタルが真似できない領域です。何十年も続く老舗の暖簾(のれん)を守り続けてきたような『勘』は、AIには再現できません。人間同士の触れ合いから生まれる温かさも、デジタルでは代替できないでしょう。」
編集長
「つまるところ、どれだけ技術が進んでも、最終的にそれを支えるのは『人』であり、『人の想い』なのかもしれませんね。本日はありがとうございました。」
対談を終えて

前回も含めて、この対談時には、あらかじめ私が質問のテーマを用意していますが、両者には一切伝えずに対談に臨んでいます。それは、用意された通り一辺倒の答えではなく、その場で出てきた生の声をお届けしたいと考えているからです。中小企業診断士でありITコーディネータでもある福田氏と、DX推進企業でありDXportal®の運営会社でもある株式会社MU代表の山田からは、打てば響くような答えが返ってくるため、私自身いつも楽しく対談を進められています。
今回両者が口を揃えて話をされたように、今や「DX」はビジネスにおいて必要不可欠な施策の一つであり、そこを避けていては今後リスクが増すとしか考えられない重要な課題です。
とはいえ、それを行うのは人間であり、AIのようなどれだけ優れたデジタルツールであろうとも、それを使いこなすのもまた人間でしかありません。企業を経営しているのも、そこで働くのも、そしてお客様も人間である以上、そこには人の想いが乗ってくるのは当たり前なのでしょう。
今後も、本サイトでは「デジタルと人の関わり」にフォーカスした、読者の皆様にとって有益な記事をご提供していきたいと考えています。
(DXportal®編集長:町田)

執筆者
DXportal編集長
町田 英伸
自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。