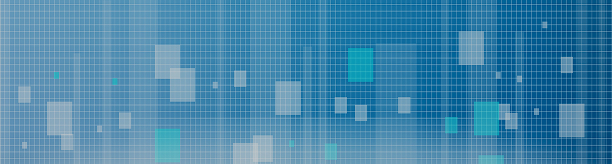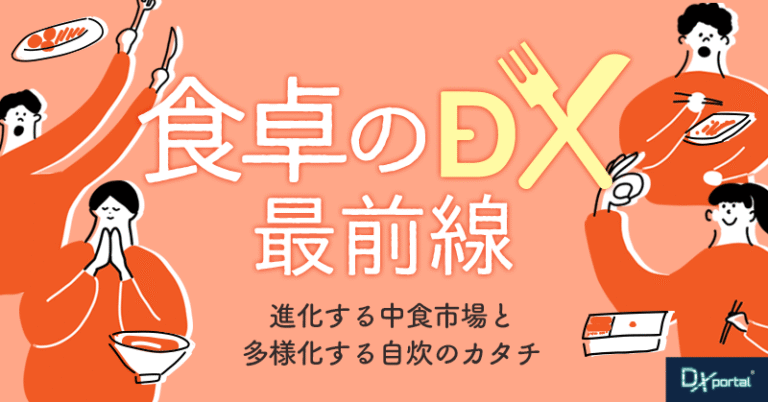
- share :
「いただきます」とともに始まる、毎日の食事。そのどこにでもあった「当たり前の風景」は、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化を背景に大きく変化しています。
かつては、手作りのご飯が並ぶ食卓を家族で囲むことが一つの理想とされていましたが、忙しい現代社会において、毎回の食事を、栄養バランスを考えながら手作りすることは決して容易ではありません。
忙しい現役世代を中心に、人気を集めているのがコンビニエンスストアやスーパーマーケットに並ぶ彩り豊かなお弁当やお惣菜、そして自宅で手軽に本格的な料理が楽しめるミールキットです。この外食と内食(自炊)の間に位置する「中食(なかしょく)」は、すでに私たちの食生活を支える存在になっています。
また、自炊のあり方も大きく変化しています。健康志向の高まりや調理家電の進化、そしてSNSを通じた情報共有などにより、新たな価値が見出されているのです。
近年、これらの食を取り巻く変化の背後には、DX(デジタルトランスフォーメーション)の存在が欠かせません。
例えば、中食市場では、オンライン注文やデリバリーサービスの導入、AIを活用した献立提案サービスなど、DXによる新たな価値が生まれています。自炊においても、レシピアプリやスマートキッチンの登場により、調理の効率化や食体験の向上が実現しています。
本記事では、進化を続ける中食市場と多様化する自炊の最新動向を分析し、それぞれのメリット・デメリット、今後の展望などを考察します。特に、DXが中食と自炊にもたらす影響に焦点を当て、具体的な事例を交えながら解説しますので、ご参考にしてください。
進化する中食市場:DXがもたらす変革

前述のように、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化を背景に、中食市場は急速に拡大しています。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの品揃えは劇的に充実してきており、またECサイトを通じたデリバリーサービスも急激に普及しました。このような、中食を取り巻く環境の変化を肌で感じている方も多いのではないでしょうか。
本章では、中食市場の最新動向を深掘りし、その進化の背景にある要因や、多様化する中食の形態、そしてDXを活用した新たな取り組み事例を紹介します。
中食市場の拡大とDX
日本の食生活は、社会構造の変化とともに大きく変化してきました。共働き世帯や単身世帯の増加、そして高齢化の進行は、人々の食に対するニーズを多様化させているのです。
特に、調理時間を短縮したい、あるいは手軽に食事を済ませたいというニーズの高まりは、中食市場が急速に拡大する大きな要因となっています。
中食への支出は年々増加傾向にあり、その市場規模は既に数兆円に達しています(参考:株式会社矢野経済研究所/惣菜(中食)・米飯市場に関する調査を実施(2024年))。この背景には、先にあげた食生活の多様化に加え、それに対応する形でコンビニエンスストアやスーパーマーケットが、商品の品質向上と品揃えの拡充を進めたことが大きく影響しています。特に、冷凍技術や調理技術の進化が、これまでネガティブなイメージを持たれがちだったお惣菜や冷凍食品の品質を飛躍的に向上させ、消費者の購買意欲を刺激する結果を生み出したと言ってよいでしょう。
これまでは「健康に悪い」というイメージが強かったお惣菜や冷凍食品ですが、健康志向や多様な食文化に対応した商品を積極的に開発しており、顧客の選択肢を広げています。
さらに、前述のECサイトを通じたデリバリーサービスの普及も、中食市場の拡大を後押ししています。今では当たり前となった、Uber Eatsや出前館といったデリバリープラットフォームは、自宅やオフィスにいながら、手軽に様々な料理を注文できる環境を提供しているのです。
多様化する中食の形態とDX
中食の形態は、弁当、惣菜、ミールキット、冷凍食品など、多岐にわたります。
弁当は、現在でもオフィスワーカーや学生にとって定番の選択肢です。コンビニエンスストアやスーパーマーケットで購入できる手軽さに加えて、最近では、健康志向に対応した高タンパク質弁当や低カロリー弁当も登場しており、選択肢の広さも魅力です。
惣菜は、スーパーマーケットやデパートの食品売り場で、家庭の食卓を彩る一品として利用されてきましたが、DXによってその提供方法が大きく変わりつつあります。
例えば、AIを活用した需要予測によって、廃棄ロスの削減と常に新鮮な商品を提供することが可能になりました。また、アプリやオンラインストアと連携し、事前に惣菜を予約・決済できるサービスも増えています。これにより、店頭での待ち時間が短縮され、消費者はよりスムーズに商品を購入できるようになりました。
さらに、健康志向の高まりから、個別の栄養バランスに配慮したパーソナル惣菜の提案も始まっており、単なる手軽さだけでなく、個々のニーズに合わせた「個別最適化」の要素が加わっているのです。
ミールキットは、レシピと必要な食材がセットになっているため、短時間で本格的な料理を作ることができます。忙しい人や料理初心者にとって便利な選択肢であり、近年市場が拡大しています。
冷凍食品は、長期保存が可能で、必要な時に手軽に調理できることから、忙しい人や一人暮らしの人に人気です。近年では、技術の進化に伴って、単に手軽なだけでなく、本格的な味わいの冷凍食品も増えており、その需要はますます高まっています。
中食に関するDXの取り組み事例
中食市場の拡大に伴い、各企業はDXを積極的に推進しています。繰り返し登場しているオンライン注文やデリバリーサービスの導入は、顧客の利便性を向上させるだけでなく、新たな顧客層の開拓にもつながっています。
例えば、大手コンビニエンスストアでは、スマートフォンアプリから事前に注文し、店舗で受け取る「ピックアップサービス」を導入しています。これにより、顧客は店舗での商品選びやレジでの会計にかかる時間を短縮し、よりスムーズに商品を受け取ることができるようになりました。このサービスは、多忙なビジネスパーソンや子育て中の家庭など、時間を効率的に使いたいというニーズに応えるものであり、利便性の向上に大きく貢献しています。
また、フードテックを活用した新たな商品やサービスの開発も進んでいます。例えば、AIを活用した献立提案サービスや、調理ロボットによる調理の自動化などがその一例です。これらの技術を活用することで、中食の品質向上や効率化、そして新たな食体験の提供が期待されます。
中食市場の課題と今後の展望
中食市場は、今後も成長が見込まれますが、いくつかの課題も存在します。
特に、健康面への配慮や栄養バランスの偏りは、早急に解決すべき課題です。前述のように、すでに健康志向の高い消費者向けの商品開発が進められていますが、ユーザーのニーズに追い付いていないのが現状です。消費者の健康志向の高まりに対応するため、各企業は、より栄養バランスに配慮した商品の開発を進めています。
単なるカロリー表示だけでなく、例えば、スマートフォンアプリと連携し、食事内容を記録・分析することで、個別の健康状態に合わせた栄養管理をサポートするサービスの提供。あるいは、アレルギーや特定の疾患を持つ人々に対応した、個別最適化された商品の提供も重要な取り組みとなるでしょう。
また、容器の使い捨て問題や食品ロスの問題も、中食市場の発展を阻害する要因です。いくら便利だとしても、中食産業の拡大が地球環境に悪影響を及ぼすようなことになれば、規制強化など様々なリスクに直面してしまいます。SDGsに代表される環境意識の高まりに答えるためにも企業はリサイクル可能な容器の使用や、食品ロス削減に向けた取り組みを強化しています。
これらの課題解決にも、DXが重要な役割を果たすと考えられます。例えば、AIを活用した栄養バランス診断サービスや、フードシェアリングプラットフォームの構築などが挙げられるでしょう。今後は、健康志向に対応した商品開発や環境に配慮した容器の使用、食品ロス削減に向けた取り組みなどが、中食市場の発展を左右する要因となるはずです。
さらに、個々のライフスタイルに合わせた多様なニーズに応える商品やサービスの提供も今後さらに重要になります。例えば、高齢者向けの宅配サービスや、アレルギー対応食の提供などは、これからより一層注目される取り組みでしょう。
中食市場は、DXを駆使しながら、多様なニーズに応え、更なる進化を遂げていくことが期待されるのです。
多様化する自炊環境と進化を支えるテクノロジー

かつては「やらなければならない家事」であった自炊は、現代において多様な価値を持つ行為として再評価されています。健康志向の高まり、食育への関心、そして趣味としての料理を楽しむ人が増える中で、自炊の形も大きく変化しているのです。
本章では、自炊をサポートするサービスやアプリ、そして調理家電の進化とスマートキッチンについて詳しく解説します。
進化する自炊を支えるテクノロジー
いくら中食が発展してきたとはいえ、費用面でも健康面でも、自炊は多くの人にとって避けては通れないものです。適度に中食も活用しつつ、自炊をしていくことは食育や食文化を守る観点からも重要でしょう。他方で、忙しい現代人にとって自炊を続けていくにはいくつかの課題があります。特に、調理時間の確保や献立のバリエーション不足は、多くの人が直面する悩みでしょう。
しかし近年、これらの課題を解決するために、ITテクノロジーやスマートキッチンなどの最新テクノロジーが活用され、自炊体験は大きく進化しています。
ここでは、近年になって実現した、ITテクノロジーを活用したいくつかの事例をご紹介します。これらのテクノロジーを活用することで、調理時間の短縮や献立のバリエーションを増やすことができるだけでなく、調理そのものをよりクリエイティブで楽しいものに変えることができます。
レシピ提案・献立作成AI
AIを活用したレシピ提案・献立作成サービスは、まるで専属シェフのように、あなたの好みや栄養バランス、そして冷蔵庫にある食材などを考慮して、最適なレシピや献立を提案してくれます。
例えば、「me:new」のようなアプリでは、AIがあなたの過去の食事履歴や好みを学習し、マンネリ化を防ぐためにバラエティ豊かな献立を提案してくれます。
また、冷蔵庫にある食材を登録しておけば、それらを優先的に消費できるレシピを提案してくれるため、食品ロス削減も期待できるのです。
オンライン食材宅配サービス
オンライン食材宅配サービスは、新鮮な食材を自宅まで届けてくれるため、買い物に行く手間を省くことができます。
なかでも「Oisix」や「大地を守る会」のようなサービスは、有機野菜や特別栽培農産物など、こだわりの食材を取り扱っており、健康志向の人に人気です。
また、ミールキットと呼ばれる、レシピと必要な食材がセットになった商品も人気を集めています。調理時間や栄養バランスが考慮されており、忙しい現代人にとって最適な選択肢となっているのです。
スマートキッチン
スマートキッチンは、IoT技術を活用し、様々なキッチン家電をネットワークに接続することで、調理の自動化やレシピ提案、食材管理など、より高度な調理体験を提供してくれる技術です。
- スマートレンジ:レシピに合わせて最適な火加減や調理時間を自動で設定し、調理をサポートする
- スマート冷蔵庫:食材の在庫状況を自動で管理し、賞味期限切れが近づいた食材を教えてくれる
- スマートスピーカー:音声でレシピを検索したり、調理タイマーをセットしたりすることができる
自炊の未来:テクノロジーと食育の融合
今後は、ITテクノロジーやスマートキッチンの普及、そして食育の推進を通じて、より多くの人が自炊を楽しみ、健康的な食生活を送ることができるようになるでしょう。
テクノロジーは、調理の効率化や献立の多様化を支援するだけでなく、食に関する知識や選択能力を高める上でも重要な役割を果たすことが期待されています。
例えば、食材の栄養価や調理方法による栄養価の変化などをデータとして提供することで、より科学的で根拠に基づいた食生活を送ることができるようになります。
また、共働き世帯の増加や生活習慣病の増加といった社会背景から、食育の重要性がますます高まっています。さらに、料理教室や食に関するイベントなども、自炊をサポートする存在として注目されており、これらの活動を通じて、食に関する知識や調理スキルを身につけることで、人々はより主体的に食生活をコントロールできるようになるでしょう。テクノロジーの発展はこうした流れを加速させます。
今後は、食育とテクノロジーが融合することで、より効果的な食育が実現できる未来が待っているのです。
例えば、AIを活用した食育アプリや、VR(仮想現実)を活用した食体験などが挙げられます。これらの技術を活用することで、子どもたちは楽しく食について学び、健康的な食習慣を身につけることができるでしょう。
自炊は、テクノロジーと食育の融合によって、より豊かで健康的な食生活を実現するための鍵として、今後ますます注目を集めていくと考えられます。
まとめ:中食と自炊の新たな関係
本記事では、進化を続ける中食市場と多様化する自炊の最新動向について解説しました。
かつては対立する存在とも思われていた中食と自炊は、現代において互いに補完し合う関係へと変化しています。
- 平日の忙しい時は中食を利用し、週末は時間をかけて自炊を楽しむ
- 健康志向の人は、栄養バランスを考えながら、中食と自炊を組み合わせる
このように、個人のライフスタイルやニーズに合わせて、中食と自炊を自由に選択できる時代になりました。今後の食生活は、さらに多様化し、個人のニーズに合わせた自由な選択肢が増えていくでしょう。
中食市場は、より多様なニーズに対応した商品やサービスを提供することで、さらに成長する可能性があります。また、自炊は、健康志向や食育への関心を背景に、新たな価値を創造し、多様なライフスタイルに合わせた形で進化していくでしょう。
食品業界、外食産業は、これらの変化を捉え、新たな商品やサービスを開発することで、顧客の多様なニーズに応えていかなければなりません。
変化を続ける食卓の未来において、中食と自炊は、互いに手を取り合いながら、私たちの食生活をより豊かにしてくれる存在となるのではないでしょうか。

執筆者
DXportal編集長
町田 英伸
自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。