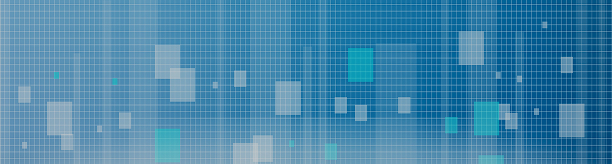その2:問い合わせ対応の自動化「エージェントAIが社内IT窓口を担う」

社内のIT部門が日々対応している問い合わせ業務。
- Wi-Fiがつながらない
- メールが届かない
- PCが重い
など、繰り返し発生するトラブル対応は、IT部門のリソースを圧迫し、本来の業務に集中できない原因にもなっています。こうした課題に対して、エージェントAI(AIチャットボット)の導入が注目されています。
自然言語処理(NLP)と業務知識を組み合わせた対話型AIが、社内の「IT窓口」として機能することで、問い合わせ対応の質とスピードが劇的に向上します。
【技術的な仕組み】
- NLP:曖昧な表現を理解し、技術的な問題にマッピング
- インテント・エンティティ抽出:目的と対象を特定(例:VPN接続トラブル、社員ID)
- ナレッジベース連携:FAQや手順書、過去の対応履歴から回答を抽出
- 実行エンジン:PowerShellやAPIで設定変更やアカウント操作を自動実行
- ログ管理と学習:履歴を記録し、次回以降の精度向上に活用
この仕組みを利用して、ある流通業では、月間2,000件以上の問い合わせのうち約60%をAIが対応。IT部門の対応時間を月100時間以上削減しました。
その3:障害対応の自動化「生成AIが初動判断まで支援する」

障害対応は、インフラ運用の中でも最もリスクと負荷が高い業務です。特に夜間や休日の対応は、限られた人員での対応が求められ、初動の遅れが業務全体に影響を及ぼすこともあります。
従来は、監視ツールがアラートを出し、担当者がログを確認し、手動で対応する流れでした。しかし、これでは対応の質が人に依存し、スピードもばらつきが出るのが課題となってしまうでしょう。
この課題に対し、最近では生成AIを活用した障害対応の自動化が注目されています。従来のルールベースAIと異なり、生成AIは以下のような高度な支援が可能です。
- ログの自然言語解析:複雑なログを人間が読むように理解し、異常箇所を抽出
- 原因推定の説明生成:障害の可能性を自然言語で説明(例:「このエラーはDB接続タイムアウトの可能性があります」)
- 初動手順の提案:過去の対応履歴やベストプラクティスをもとに、最適な初動手順を提示
- スクリプト生成:必要な対応スクリプト(再起動、ログ取得、設定変更など)をその場で生成
生成AIが障害対応の初動を支援するプロセスは、従来の監視システムと連携することで、極めて迅速な対応を可能にします。まず、従来の監視ツールが検知したCPU負荷やログの異常といったデータを生成しAIエンジンに連携するのです。
生成AIは、連携された大量のログやアラートデータを人間が読むように自然言語で解析し、障害のパターンや複雑な相関関係を瞬時に特定します。その結果、過去の履歴を参照しながら最も可能性の高い原因を推定し、その推定結果を技術的な専門用語ではなく、人間が理解しやすい自然言語で説明文書として出力するのです。
最終的に、特定された原因に基づき、最適な復旧のための初動手順や、実行可能なスクリプトコードを生成し、担当者に提示する流れとなります。
例えば、生成AIによる障害対応を自動化したあるIT企業では、生成AIが夜間の障害ログを解析し、不要な通知を抑制すると同時に、必要な初動を自動実行することで復旧時間を短縮しました。また、建材卸企業における事例では、VPN障害時に生成AIがISP障害か社内ネットワーク障害かを自然言語で説明し、ルーター再起動スクリプトを自動生成することで、対応時間が15分から2分に短縮されたといいます。
生成AIは、単に作業を自動化するだけでなく、人間の判断を補完する高度な知能として、障害対応の質とスピードを大きく向上させる手段となり得るでしょう。
まとめ:インフラ運用のDXは企業の「見えない業務」を変える
DXは事務作業の効率化という表面的な改善にとどまるものではありません。インフラ運用こそ、企業のデジタル基盤を支える「見えない業務」であり、ここにDXを適用することで、業務の質、スピード、継続性が劇的に向上するのです。
本記事で紹介した「3つの自動化」戦略は、インフラ運用の構造的な課題を根本から解決します。
- ジョブスケジューラやIaCで定型作業や構成管理を自動化・標準化し、人的ミスを排除する
- エージェントAIで問い合わせ対応を自動化し、IT部門のコア業務への集中を促す
- 生成AIで障害対応の初動判断とスクリプト生成を支援し、夜間・休日の運用リスクを劇的に低減する
これらを段階的に導入することで、IT部門の負担を減らし、企業全体の生産性を底上げすることが可能です。
インフラ運用を変革することは、属人化リスクを排除し、変化に強い「競争優位性の高い経営基盤」を築くことに他なりません。
貴社がこのインフラDXを具体的な戦略として推進するためには、まずは自社の現状を客観的に評価し、どの自動化から着手すべきか、最適なステップを踏むことが求められるでしょう。

執筆者
株式会社MU 営業部
帯邉 昇
新卒で日本アイ・ビー・エム株式会社入社。ソフトウェア事業部でLotus Notesや運用管理製品Tivoliなどの製品担当営業として活動。その後インフォテリア株式会社、マイクロソフト株式会社で要職を歴任した。キャリア30年のほとんどを事業立ち上げ期のパートナーセールスとして過ごし、専門はグループウェアやUC、MA、SFA、BIなどの情報系で、いわゆるDXの分野を得意とする。(所属元)株式会社エイ・シームジャパン。