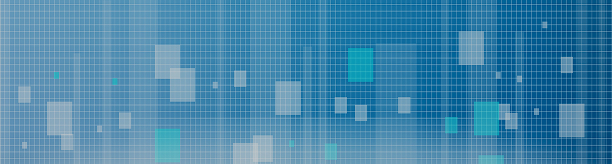- share :
モバイルオーダーやキャッシュレス決済の普及が象徴するように、デジタルトランスフォーメーション(DX)は飲食店にとって、売上向上という光をもたらす重要な経営戦略となりました。しかし、その裏側には、事業継続を脅かすサイバー攻撃という影が潜んでいます。
2025年9~10月に大企業アサヒグループホールディングスが受けたランサムウェア攻撃は、中小の飲食店にとっても極めて切実な問題です。この攻撃により、アサヒが受発注システムの停止にまで追い込まれた事件は、飲食業界にも大きな影響を与えました。直接攻撃にさらされたアサヒだけでなく、アサヒの商品を取り扱うすべての業者、場合によっては消費者までもが被害者である、といっても過言ではないでしょう。
この記事の筆者である私(DXポータル編集長)は、もう一つ飲食店DXアドバイザーという肩書も持っていますが、その立場からしても、デジタルを悪用したこの攻撃に怒りを感じています。それと同時に、DX推進が私たちにもたらしてくれる様々な恩恵の裏側にある、リスクに改めて目を向ける重要性を痛感しました。
さらに言えば、今回の事件のように飲食店が巻き込まれる形で「被害者」になるリスクだけでなく、意図しないうちに間接的な「加害者」になってしまうリスクすらあると憂慮しています。
本記事では、デジタル化の光と影を徹底解説しながら、大企業で起きた事件から中小飲食店が学ぶべき教訓を提示します。
大企業アサヒの危機が飲食業界に与える現実的影響

アサヒの事件は、「大企業の話」と切り捨ててはいけません。実際に、今回の事件の影響を受けて、一部の飲食店ではアサヒ関係の商品の品薄状態に陥りました。デジタル社会では、巨大な企業の危機は必ずサプライチェーンを通じて、私たちのような小規模事業者の経営にも現実的な影響を及ぼします。
この章では、アサヒグループを襲ったサイバー攻撃の具体的な概要と、その被害がどのように飲食業界全体に波紋を広げたのかを解説します。
2025年アサヒグループを襲ったランサムウェア被害の概要
ビールや飲料を提供するアサヒグループホールディングスは、2025年9月から10月にかけて、極めて深刻なサイバー攻撃を受けました(参考:サイバー攻撃によるシステム障害発生について(第4報)/アサヒグループホールディングス公式サイト)。
この攻撃はランサムウェアという、身代金要求型ウイルスによるものでした。ランサムウェアとは、システムに侵入した第三者が企業内のファイルやデータを暗号化し(スクランブルをかけ)、使用不能な状態にした上で、その解除と引き換えに金銭(身代金)を要求する不正プログラムです。
本記事執筆時点(2025年11月1日)では、調査が継続中であり、被害状況の全容は明らかになっていないものの、この攻撃によりアサヒの受発注システムや工場の一部システムにまで影響が及び、業務が一時的に停止するという事態に至りました。また一部個人情報が流出した可能性があると公表されています。
被害を最小限に抑えるために、アサヒはランサムウェアの攻撃を受けたシステムを遮断しましたが、その結果、国内グループ各社の受注・出荷などに甚大な影響が出た他、社外からのメールを受信できない状況に追い込まれました。事業の根幹にかかわるシステムが機能停止に追い込まれたことで、同社の事業継続の根幹が脅かされたといえます。
2024年には、KADOKAWAが同様にランサムウェアによる攻撃を受け、多額の特別損失(24億円)を計上する事例も発生しています。こうした事例を見ても、ランサムウェア攻撃は被害が長期化・甚大化する傾向があることは明らかです。
アサヒのような大企業が、最先端のセキュリティ対策を講じていたにもかかわらず、外部からの不正アクセスを防ぎきれなかった事実は、デジタル化を進めるすべての企業にサイバー攻撃のリスクと向き合う必要性を突きつけています。
大企業のシステム停止が中小飲食店にもたらした波紋
飲食店DXアドバイザーの視点から見ると、このアサヒの危機は中小の飲食店にとっても他人事ではありません。大企業がシステム停止に陥った場合、その影響は必ずサプライチェーン(供給網)を通じて末端にまで及びます。
アサヒのケースでは、工場や物流システムが停止した結果、取引業者である酒販店や卸業者の業務を混乱させました。その具体的な影響は、プロ野球の祝勝会で恒例のビールかけが取り止めとなり、シャンパンファイトに変更されたという報道からも伝わってきます。ビールという主力の供給が不安定になることは、年末商戦を控える飲食業界にとって、極めて深刻な問題です。
この事件の影響はビールだけに留まりませんでした。例えば、ある福岡の飲食店では、アサヒ製品のビール不足は解消しつつあるものの、ハイボールやチューハイに不可欠な炭酸のガスボンベの入荷が困難になったり、人気サワーの提供に使う大容量のカルピスが入荷できず、小さいペットボトルで代用を余儀なくされたりしているとのことです。
アサヒ製品が品薄になると他社の商品へ注文が殺到するため、対応しきれなくなった各企業が出荷規制を始めるなどの事態も起こり始めており、この状況が続けば、年末商戦を迎える飲食業界に多大な影響を及ぼすことは必至でしょう。
この事実が示すのは、一つの企業が受けた攻撃が、デジタルで強く結びついたサプライチェーンを通じて、私たちの飲食店の仕入れや在庫管理にまで直接、かつ不可避な影響を及ぼすということです。これは、現代のデジタル社会が抱える構造的なリスクと言えます。つまり、私たちは、自店舗のデジタル化だけでなく、取引先から波及するリスクにも備える必要があるのです。
中小飲食店にDXがもたらす「光」とその不可避性

デジタル化が進む現代において、DXは単なる流行の言葉ではありません。飲食店にとっても、売上を伸ばし、経営の非効率性を解消するための重要な戦略です。「今回のような事件に巻き込まれることを避けるために、DXには取り組まない」という消極的な選択肢はもはや存在しないとさえ言えるでしょう。
この章では、私たちがDXから享受できる「光」の側面と、それがもはや避けられない経営課題である理由を解説します。
停滞感を打破するDX:飲食店経営を変革するデジタルの力
DXとは、デジタル技術を用いて、ビジネスモデルや組織のあり方そのものを変革し、競争優位性を確立する取り組みです。私たち飲食店経営者が抱える、人手不足や原材料高騰といった構造的な停滞感を打破する上で、DXは不可欠な要素となっています。その主なメリットは、次のようなものです。
- 顧客体験(CX)の向上と売上の創出:モバイルオーダーやキャッシュレス決済を導入することで、お客様の利便性が向上し、新しい顧客層の獲得に繋がる。また、顧客データを分析することで、個々のお客様に合わせたパーソナライズされたメニュー提案やキャンペーンの展開が可能になり、客単価やリピート率を向上できる
- 業務効率化による生産性の向上:POS(販売時点情報管理)と連動した自動発注システムやAIを活用した需要予測は、経験則に頼っていた仕入れや在庫管理の精度を向上させる。これにより、フードロス削減と過剰労働の抑制を同時に実現でできる
- 新しい経営戦略の推進:クラウドサービスを活用した多店舗管理やリモートでの経営分析が可能になる。これにより、経営者自らが現場にいなければならない時間を減らし、次の事業展開や新しいコンセプトを考える時間を作り出すことも可能にする
競合店がデジタル化を進める中、DXはもはや生き残りに不可欠な要素であり、これなくして新しい経営戦略の推進は図れないのです。
デジタル化の浸透が生んだ「情報資産」という新たなリスク源
DXがもたらす「光」は極めて大きいものです。しかし、デジタル化の浸透は同時に、私たち飲食店に「情報資産」というリスク源を生み出しました。
サービス(予約、決済、仕入れ)がデジタル化することで、飲食店には膨大な情報資産が蓄積されるようになりました。
- 常連客の氏名や連絡先
- 決済情報
- 従業員の個人情報
- 店舗の売上
- レシピにかかわる情報(使用している食材や産地、仕入れ価格、購入頻度など)
これらのデータすべてが店舗にとっては機密情報であり、経営においてかけがえのない価値を持ちます。裏を返せば、サイバー犯罪者から見ても、極めて価値ある「宝の山」となっているのです。
この情報資産を守り抜くことこそが、デジタル時代における経営の責務だと言えるでしょう。DXによって得られた光を享受し続けるためにも、私たちはこの「影」の存在を深く理解し、適切な対処を講じなければなりません。

執筆者
DXportal編集長
町田 英伸
自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。