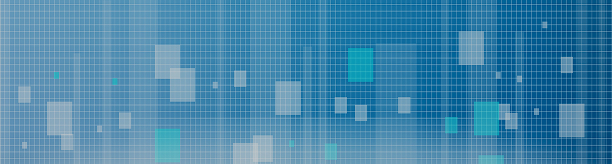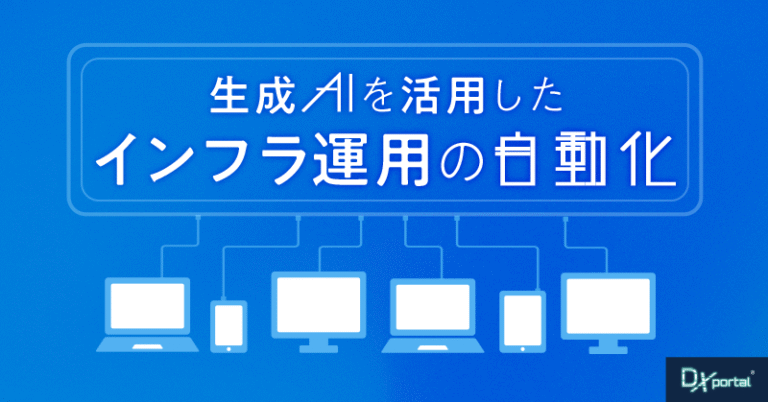
- share :
デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みが「事務作業の効率化」に留まっている企業は少なくありません。しかし、DXの本質は、業務をただデジタルに置き換えるのではなく、業務そのものを変革し、新たな価値を生み出すことにあるのです。
特に最近では、企業のデジタル基盤を支えるインフラ運用部門こそ、長年の属人化やリソース不足といった課題を抱え、今、DXによる変革が強く求められています。
本記事では、従業員1,000名規模の企業を想定し、このインフラ運用にDXを適用することで実現できる、「定型作業」「問い合わせ対応」「障害対応」という3つの分野における具体的な自動化戦略を、最新の生成AIの活用事例も交えて解説します。
インフラ運用部門の負担を劇的に軽減し、貴社のITリソースを戦略的な業務へと振り向けるための、意思決定を強力に支援できるはずです。
インフラ運用のDXが注目を集める構造的な背景

多くの企業において、営業や経理といった目に見える業務のデジタル化が進む一方で、システムの安定稼働を支えるインフラ運用部門は、長年の課題を抱えたまま、経営的なボトルネックとなっています。特に中小企業では、限られたITリソースが古い運用手法に縛られ、本来の戦略的な業務に割けないという状況が見られます。
本章では、インフラ運用の現状が抱える三つの深刻な課題、すなわちDXが必要とされる構造的な背景について論じます。これらの構造的な課題を解決し、企業の競争力を取り戻すことこそが、インフラDXによる「3つの自動化」の必要性を示す論拠となるのです。
運用ノウハウの属人化とブラックボックス化
インフラ運用における最大の構造的な問題の一つが、ノウハウの属人化です。長年システムを運用してきた特定の担当者が、サーバーの設定、障害対応の手順、セキュリティパッチの適用ルールなど、多岐にわたる重要な知識を個人の中だけに抱え込んでいるケースが散見されます。
これは、インフラ運用がシステムの「裏側」であり、業務手順が明文化されていない、あるいはドキュメントが更新されていないために発生するものです。結果として、その担当者の異動、退職、あるいは長期休職などによって、システムの維持管理が不可能となる深刻なリスクに直結します。
システム構成がブラックボックス化すると、新しい技術の導入やセキュリティ強化などの変革を試みようとしても、その都度、膨大な時間とコストをかけて現状調査から始めざるを得なくなるでしょう。
IT人材不足と技術の加速度的な複雑化
企業がインフラ運用のDXに踏み切らなければならない背景には、IT人材の供給不足という社会的な要因も存在します。特に中小企業においては、IT部門の人員は限られており、最新技術に対応できる専門知識を持った人材の確保は困難な状況が続くばかりです。
その一方で、ITインフラの技術はクラウド化、コンテナ技術、ハイブリッド環境の普及によって、加速度的に複雑化しています。従来のオンプレミス運用知識だけでは対応しきれない、高度なスキルが求められる状況です。
限られた人員が、従来のレガシーシステムと最新のクラウド技術の両方に対応し、しかも属人化したシステムの維持管理も担わなければならないという構造的な疲弊が、インフラ運用の品質低下とイノベーションの停滞を招いています。
運用コストの硬直化と隠れた機会損失
インフラ運用にかかるコストは、多くの場合、人件費と保守費用が中心となり、固定費として硬直化しやすい性質を持ちます。特に、属人化したシステムは、担当者が退職してもその穴を埋めるための人件費が発生し、保守ベンダーへの依存度が高まることで、費用は削減しにくい状態になります。
さらに深刻なのは、「隠れた機会損失」です。IT部門の限られたリソースが、定型的な監視やトラブルシューティングといった「守りの運用」に終始してしまうと、本来行うべき「攻めのDX」、すなわち新しいビジネスモデルの創出や、基幹システムの戦略的な改善といった業務に時間を割けなくなります。この運用コストの硬直化と機会損失こそが、企業の成長を阻害する見えない経営リスクとなっているのです。
その1:定型作業と基盤管理の自動化「人がやらなくていいことは、機械に任せる」

企業のIT部門が直面する大きな課題の一つは、周期的に繰り返される定型的な作業と、人の手による複雑な基盤管理に貴重なリソースが奪われている点です。バックアップやサーバーの設定変更といった作業は、手間がかかる上に人の介入によるミスが発生しやすい性質を持ちます。
そこで本章では、インフラ運用のDXにおける第一のステップとして、これらの「人がやる必要のない業務」を機械に任せる具体的な手法を解説します。ジョブスケジューラによる定型作業の自動化、IaC(Infrastructure as Code)による基盤構成の標準化、そしてAIによる監視の高度化を通じて、人の手を介さない安定運用を実現する方法を解説します。
ジョブスケジューラによる定型作業の自動化
インフラ運用では、毎日・毎週・毎月といった周期で繰り返される作業が数多く存在します。例えば、次のような作業を考えてみてください。
- 毎朝5時にバックアップを取得
- 毎週月曜にログファイルを圧縮・アーカイブ
- 毎晩22時に不要な一時ファイルを削除
- 毎月1日にユーザーアカウントの棚卸しレポートを生成
これらはすべて、ジョブスケジューラを使えば自動化可能です。
Windows環境では「タスクスケジューラ」、Linuxでは「cron」が基本ですが、より高度な運用には「JP1」「Systemwalker」などの商用ツールも活用されています。
例えば、ある製造業では、生産管理システムのバックアップをジョブスケジューラで自動化。障害発生時には「ログ収集→圧縮→メール通知」までを自動化し、対応時間が平均30分から5分に短縮されました。
IaC(Infrastructure as Code)による構成管理の標準化
IaCは、インフラ構成をコードで定義・管理する手法です。
従来は「手順書を見ながら手動で設定」していたサーバーやネットワークの構成を、コードを実行するだけで再現可能にします。
代表的なツールには、次のようなものがあります。
- Terraform:AWS、Azure、GCPなどのクラウド環境をコードで構築
- Ansible:OS設定、ミドルウェア導入、ユーザー管理などを自動化
- Pulumi / Chef / Puppet:より複雑な構成管理に対応
IaCの導入により、再現性・バージョン管理・監査対応・教育コスト削減といったメリットが得られます。
例えば、ある卸売業では、TerraformとAnsibleを組み合わせてAWS上のサーバー構築を完全自動化。構築時間が1日→30分に短縮され、運用ミスもゼロになりました。
AIによる状況判断型監視:通知の「意味」を理解する
従来の監視は、CPU使用率が90%を超えたら通知するといった、閾値(しきいち)ベースの死活監視(あらかじめ設定した基準を超えたらアラートを出す監視)が中心でした。
しかしこの方法では、バッチ処理などの一時的な負荷でもアラートが鳴り、誤検知や対応漏れが頻発します。
そこで注目されているのが、AIによる状況判断型の監視です。AIはログ、リソース使用状況、時間帯、過去の障害履歴などを総合的に分析し、意味のある通知だけを出します。
あるIT企業では、夜間バッチ処理中のCPU高負荷を「正常」と判断し通知を抑制。メモリ急増時にはログ肥大化を検知し、自動でローテーション(ログファイルが肥大化するのを防ぐために、定期的に古いログをアーカイブ(圧縮)したり削除する仕組み)しています。これにより誤検知が80%減少し、夜間対応の負担が大幅に軽減されました。

執筆者
株式会社MU 営業部
帯邉 昇
新卒で日本アイ・ビー・エム株式会社入社。ソフトウェア事業部でLotus Notesや運用管理製品Tivoliなどの製品担当営業として活動。その後インフォテリア株式会社、マイクロソフト株式会社で要職を歴任した。キャリア30年のほとんどを事業立ち上げ期のパートナーセールスとして過ごし、専門はグループウェアやUC、MA、SFA、BIなどの情報系で、いわゆるDXの分野を得意とする。(所属元)株式会社エイ・シームジャパン。