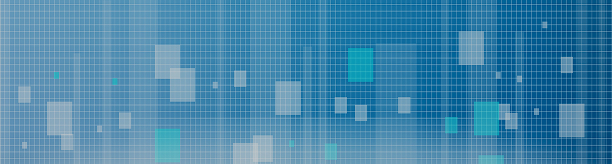- share :
DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれて久しい昨今、従来からグローバルに展開してきた企業を中心に、日本企業においても世界を舞台にしたDX戦略が積極的に推進されています。
大企業のDXの取り組みは目覚ましいものがあるとはいえ、DXは決して一部の大手だけの話ではありません。中小企業であっても、グローバルな視点を取り入れたDXを導入することで、海外市場への参入や競争力強化などを達成することができるのです。大手の取り組みからも学べることは少なくありません。
そこで本記事では、日本発のグローバル企業3社のDX戦略の中から、中小企業が学ぶべき成功事例を紹介します。
日本を代表するグローバル企業である三菱UFJ銀行、トヨタ自動車、味の素の3社がどのようにDXを推進し、グローバル展開を加速させているのかを具体的に見ていきます。各社の取り組みから、中小企業が自社のDX戦略に活かせるヒントを探ることで、海外市場での成功に繋がる道筋が見えてくるでしょう。
1. 三菱UFJ銀行:AIで金融サービスを高度化

三菱UFJ銀行は、AIやデータ分析を活用した金融サービスの高度化を図り、世界水準の金融サービスを提供しています。
金融業界を取り巻く環境変化に対応するため、DXを重要な経営戦略と位置づけ、積極的に推進。AIやデータ分析を活用した顧客サービスの向上、業務効率化、新たな金融サービスの開発など、様々な取り組みを実施しています。
AIとデータ分析の活用
三菱UFJ銀行は、AIを活用した顧客対応の自動化や、データ分析に基づいた融資審査の効率化などに力を入れています。例えば、AIチャットボットを活用した24時間365日の顧客対応や、AIによる不正取引の検知など、様々な分野でAIが活用されていることは広く知られているでしょう。これにより、顧客サービスの向上や業務効率化を実現しているのです。
特に注目すべきは、AIによる不正取引の検知です。グローバルに展開する金融機関にとって、各国の規制遵守やマネーロンダリング対策は極めて重要です。AIが膨大な取引データを分析し、異常パターンを検知することで、リスクを早期に特定し、迅速な対応が可能となります。
これは、各国の法規制に柔軟に対応しながら、コンプライアンスを強化する上で不可欠な取り組みであると言えます。
グローバル展開における柔軟なAI活用
三菱UFJ銀行は、AIやデータ分析を活用した金融サービスを世界中で展開しています。なかでも注目すべき点は、その柔軟な活用の仕方です。金融に関するルールや市場の動向などは国ごとに異なる場合も多いため、日本の状況に合わせたツールやサービスを開発しても、グローバルな展開ができない場合も少なくありません。
三菱UFJ銀行は、各国の緊急規制や顧客ニーズに合わせて、柔軟にサービスをカスタマイズすることで、世界中で顧客を獲得し、事業を拡大しています。
例えば、ある国ではオンラインバンキングの利用率が低い場合、その国の文化やインフラに合わせたオフラインでの顧客接点や、対面サービスとの連携を強化するAIソリューションを導入するといった具合です。
このように、ローカライズされたDX戦略を展開することで、世界中の多様な顧客に最適な金融サービスを提供し、信頼を築いています。
中小企業が学ぶべき点
中小企業が三菱UFJ銀行の事例から学ぶべき点は、顧客データを活用したグローバル展開です。
世界中の顧客データを分析し、それぞれのニーズに合った商品やサービスを提供することで、海外市場での競争力を高めることができます。
また、AIやデータ分析を活用した業務効率化も参考になります。 中小企業においても、RPAなどのツールを活用することで、海外拠点の業務効率化を図ることができるでしょう。
三菱UFJ銀行のように、AIを活用した顧客対応の自動化や、データ分析に基づいた業務効率化は、中小企業にとっても有効な手段です。
中小企業でも、顧客管理システムや営業支援ツールなどを導入し、顧客データの収集・分析・活用を進めることができます。
2. トヨタ自動車:MaaSでモビリティを変革
トヨタ自動車は、MaaS(Mobility as a Service:マース)プラットフォームの開発を進め、世界のモビリティ変革を目指しています。MaaSとは、電車やバス、タクシー、カーシェア、レンタサイクルなど、あらゆる交通手段をITで連携させ、スマートフォンなどから検索・予約・決済を一括して行えるようにするサービスのことです。利用者は、自分の移動ニーズに合わせて最適な交通手段を組み合わせることが可能になります。
世界的な自動車メーカーでありながら、従来の「車を売る」ビジネスモデルにとらわれず、この新たなモビリティサービスを提供していることは、多くの企業にとって示唆に富んでいるでしょう。MaaSプラットフォームを通じて、移動手段の多様化、都市交通の効率化、顧客体験の向上などを目指しています。
MaaSプラットフォームの開発とデータ活用
トヨタ自動車は、世界中の交通データを収集・分析し、最適な移動手段を提供するMaaSプラットフォームの開発を進めています。
例えば、スマートフォンアプリを通じて、公共交通機関の検索や予約、タクシーの配車、レンタカーの予約などを一括で行えるサービスを提供しています。これにより、顧客はより便利で快適な移動体験を得ることができるでしょう。
特に重要なのは、リアルタイムの交通データと移動ニーズの分析です。世界の様々な都市における交通渋滞情報、公共交通機関の運行状況、イベント情報などをリアルタイムで把握し、最適な移動ルートや手段を提案することで、利用者の利便性を飛躍的に向上させています。
これは、単に車両を提供するだけでなく、「移動」という顧客体験全体をデジタル技術でデザインするアプローチであると言えるでしょう。従来のサービスでは分断されていた情報がMaaSによって一元化され、個々の利用者の状況に合わせた最適な移動が実現される点が画期的なのです。
グローバルなモビリティサービス
トヨタ自動車は、MaaSプラットフォームを通じて、世界中で様々なモビリティサービスを展開しています。
各国や地域の交通事情に合わせて、最適な移動手段を提供することで、世界中の人々の移動をサポートしているのです。
例えば、交通インフラが未整備な地域では、オンデマンドの小型車両シェアリングサービスを導入したり、都市部では相乗りサービスを強化したりするなど、地域ごとの特性に応じた柔軟なサービス設計を行っています。
これにより、単一のサービスモデルを押し付けるのではなく、現地のニーズに根差した形でモビリティソリューションを提供し、顧客に受け入れられる事業を構築しています。
中小企業が学ぶべき点
中小企業がトヨタ自動車の事例から学ぶべき点は、世界市場における新たな価値提供です。既存のビジネスモデルにとらわれず、世界市場における新たな価値提供を模索することで、グローバルニッチ市場を開拓することができます。
また、顧客体験を重視したサービス開発も重要です。MaaSプラットフォームは、世界中の顧客にとって便利な移動手段を提供することで、顧客体験を向上させています。
トヨタ自動車のように、世界中の交通データを収集・分析し、最適な移動手段を提供するMaaSプラットフォームの開発は、中小企業にとっても参考になる取り組みです。
中小企業でも、地域に密着したMaaSプラットフォームを開発したり、特定の顧客層に特化したモビリティサービスを提供したりするなど、様々な可能性が考えられます。
例えば、特定の観光地における移動手段の最適化や、高齢者向けの移動サポートサービスなど、ニッチな市場でデジタル技術を活用した独自の価値を提供できる可能性を秘めています。
3. 味の素:研究開発のDXで世界の食卓を変える

味の素は、研究開発プロセスにDXを導入し、効率化やスピードアップを図っています。
食品メーカーとして、データサイエンスやAIを活用した研究開発、世界中の顧客ニーズの把握、製品開発の迅速化など、様々な取り組みを実施。中小企業においても、研究開発にDXを導入することで、グローバル市場における競争力を強化することができます。
研究開発におけるDXとデータサイエンスの活用
味の素は、世界中の食文化や顧客データを分析し、それぞれのニーズに合った製品開発を行っています。また、AIを活用した新素材の開発にも取り組んでいます。
例えば、過去の膨大な研究データや、最新の科学論文などをAIに学習させることで、新たな素材の開発期間を短縮したり、より効果的な成分を探索したりすることが可能になっているのです。
この取り組みの核心は、データサイエンスを駆使した仮説検証の効率化です。従来、長い時間を要していた実験と試作のプロセスを、AIによるシミュレーションや予測分析で大幅に短縮できます。これにより、新製品の開発サイクルを加速させ、グローバル市場のトレンド変化に迅速に対応できるようになるでしょう。
グローバルな製品開発
味の素は、世界中の食文化や顧客データを分析し、それぞれの地域に合った製品開発を行っています。これにより、世界中の顧客に満足してもらえる製品を提供し、グローバル市場でのシェア拡大を目指しています。
例えば、各国の食習慣や嗜好に合わせたレシピを開発したり、宗教上の理由で食べられない食材を使わない製品を開発したりするなど、様々な工夫を凝らしているのです。これは、単に製品を輸出するだけでなく、現地の食文化や慣習に深く根ざした製品開発を行うことで、顧客からの支持を得る戦略と言えます。
デジタル技術を用いることで、これらのローカルニーズを効率的に収集・分析し、製品開発に反映させている点が特筆されるでしょう。
中小企業が学ぶべき点
中小企業が味の素の事例から学ぶべき点は、データサイエンスやAIを活用したグローバル研究開発です。味の素が世界中の食文化や顧客データを分析しているように、それぞれの国や地域のニーズに合った製品を開発することで、グローバル市場でのシェア拡大を目指すことができるでしょう。
また、顧客ニーズの把握も重要です。 世界中の顧客データを分析し、顧客ニーズに合った製品を開発することで、グローバル顧客満足度を高めることができます。
味の素のように、データサイエンスやAIを活用した研究開発は、中小企業にとっても有効な手段です。
中小企業でも、研究開発データを蓄積・分析したり、AIを活用した研究開発ツールを導入したりすることで、より効率的かつ効果的な研究開発を進めることができます。特に食品業界においては、世界中の食文化や顧客データを分析することで、新たな市場ニーズを発掘し、グローバル展開に繋げることが可能です。
例えば、SNSデータやオンラインアンケートを通じて、海外の消費者の食の好みやトレンドを把握し、それに基づいた商品開発を行うことも有効なアプローチとなります。
まとめ:中小企業のグローバル展開を加速するDX戦略
本記事では、日本発のグローバル企業3社のDX戦略の中から、中小企業が学ぶべき成功事例を紹介しました。各社の事例から、中小企業がグローバルな視点でDXを導入する際のヒントや注意点が見えてくるでしょう。
DXは、決して大企業だけの取り組みではありません。 中小企業においても、グローバルな視点を取り入れたDXを導入することで、世界市場で活躍する企業へと成長することができます。
ぜひ本記事を参考に、自社のグローバルDX戦略を検討してみてください。

執筆者
DXportal®運営チーム
DXportal®編集部
DXportal®の企画・運営を担当。デジタルトランスフォーメーション(DX)について企業経営者・DX推進担当の方々が読みたくなるような記事を日々更新中です。掲載希望の方は遠慮なくお問い合わせください。掲載希望・その他お問い合わせも随時受付中。