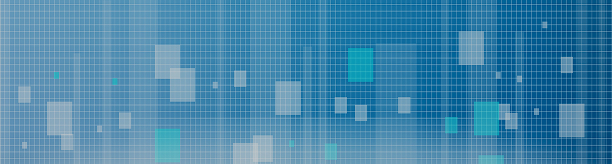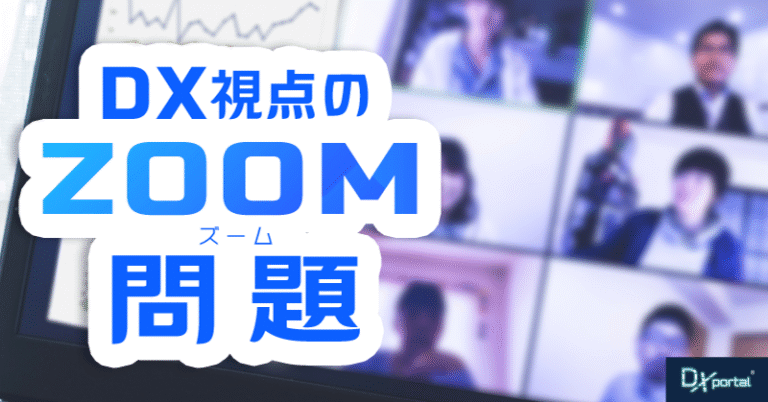
- share :
コロナ禍をきっかけに急速に普及したZoom。このツールが私たちの働き方やコミュニケーション方法に与えた影響は非常に大きなものです。
本記事では、DXの視点からZoomを再評価したうえで、セキュリティ問題の最新情報とZoomに代わる新たなコミュニケーション手段について解説します。
仕事やプライベートのやり取りにZoomを使用されている方は、この機会にぜひご一読いただき、ニューノーマルで押さえておくべきセキュリティ問題の対処法への理解を深めてください。
DX推進の一助となったZoom:その功績と現状
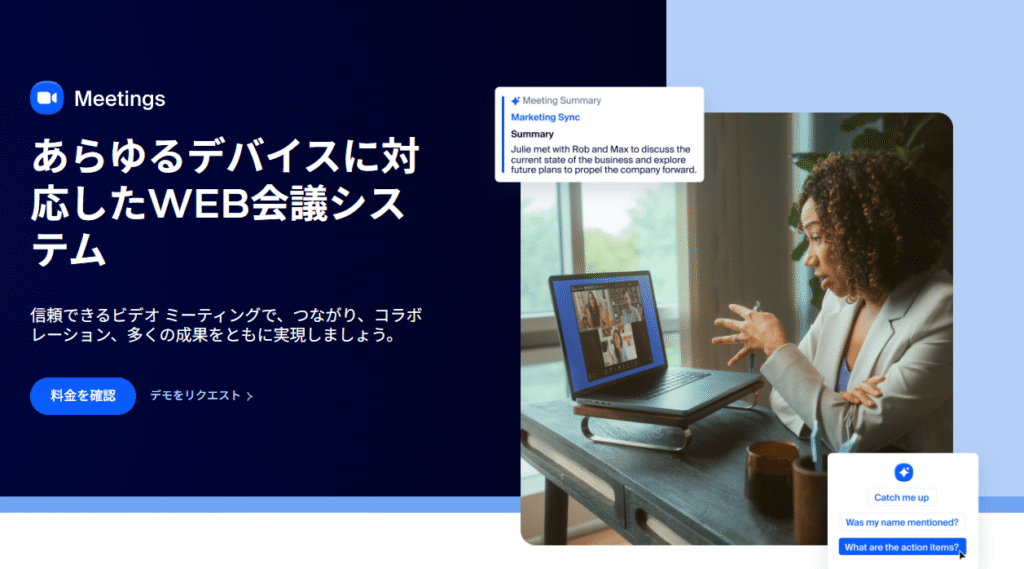
ZoomがDX推進に貢献した背景には、このツールが単なるオンライン会議ツールではなく、様々な革新的な機能と、社会の変化に合わせて柔軟に進化を続けていることがあります。
リモートワークと働き方改革の推進
Zoomは、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能にし、リモートワークやハイブリッドワークの普及を強力に後押ししました。
リモートワークの普及は、従業員にとっては通勤時間の節約、より効率的な働き方の実現に繋がりました。企業にとっても、オフィススペースの削減や優秀な人材の獲得など、コスト削減と競争力強化の両面でポジティブな影響を与えました。
コミュニケーションの活性化と新たなビジネスモデルの創出
Zoomは、ウェビナーやバーチャルイベントといった、参加者のエンゲージメントを高める新たなコミュニケーションの形を生み出しました。
- チャット機能
- Q&A
- 投票機能
- ブレイクアウトルーム
これらの双方向性(インタラクティブ性)を強化する機能により、企業は顧客との接点を増やし、単なる情報伝達に留まらない濃密で包括的な体験の提供が可能になりました。これにより、顧客満足度向上と売上増加を達成できるようになったのです。
例えば、自動字幕機能や同時通訳機能は、聴覚に障がいのある方や外国語話者といった多様な参加者に対して、アクセシビリティ(利用しやすさ)を大きく改善し、インクルーシブ(包摂的)なコミュニケーションを実現しています。また、オンライン教育や遠隔医療など、Zoomを活用した新しいビジネスモデルも次々と生まれています。
デジタル人材育成と組織文化の変革
Zoomの普及は、従業員のデジタルスキル向上を促進し、組織全体のDXリテラシーの底上げに貢献しました。これは、単に会議を行う技術を習得したというだけでなく、デジタル環境で働くための基礎体力を養ったことを意味します。
特に、オンラインでの共同作業(コラボレーション)や情報共有が日常化したことで、組織文化そのものに変化のきっかけが生まれました。従来の「対面・紙ベース」の文化から、「情報がデジタルで共有されること」を前提とした文化への移行が加速したのです。
この変化は、意思決定のスピードアップや、部門間の壁を超えた連携の容易化といった効果をもたらし、結果として組織がより俊敏(アジャイル)に、そして革新的(イノベーティブ)な思考を取り入れやすい土壌を形成しています。
プラットフォームとしての進化:API連携とエコシステムの拡大
Zoomは、API連携を強化し、様々なビジネスツールとの連携を可能にしました。これにより、ワークフローの効率化やデータの一元管理が実現し、企業の生産性向上に貢献したのです。
また、Zoom App Marketplaceを通じて、サードパーティ製のアプリを自由に利用できるエコシステムを構築し、さらなる利便性向上と新たな価値創造を可能にしています。
AI技術の導入と会議の生産性・利便性の向上
Zoomは、AI技術を積極的に導入し、会議の生産性向上と利便性の強化を図っています。それは、例えば次のような機能です。
- 会議の自動文字起こし
- 要約機能
- 背景のバーチャル変更
- 顔認識による参加者名の自動表示
こうした次々に提供される新機能は、議事録作成の手間を削減し、情報伝達の正確性を高めることで、会議の生産性向上を実現しています。また、自動字幕や同時通訳などの機能は、聴覚に障がいのある方や外国語話者の参加を容易にし、コミュニケーションの包括性(インクルーシブネス)とアクセシビリティを大きく向上させているのです。
これにより、参加者全員にとってより質の高い体験を提供できるようになりました。
このように、Zoomは単なるオンライン会議ツールとしてだけでなく、DX推進の加速装置として、多岐にわたる分野で革新的な変革をもたらしてきました。
Zoomは、今後もAI技術の進化や社会の変化に合わせて、さらなる進化を遂げていくことが期待されます。
Zoomのセキュリティ問題と最新の対策

Zoomが私たちのコミュニケーションを革新した一方で、ニュースでも報じられたようにZoomに関連したセキュリティ問題が浮上したことは否めません。Zoomはこれらの課題に真摯に向き合い、継続的な対策を講じてきました。
ここでは、Zoomのセキュリティ問題と最新の対策について、より詳しく解説します。
過去のセキュリティ問題
- Zoom Bombing(ズーム爆撃):第三者が無許可で会議に侵入し、不適切なコンテンツを共有する行為が多発。これにより、会議の妨害やプライバシー侵害が発生した
- データセンターの接続問題:一部のユーザーのデータが、意図しない国のデータセンターを経由していたことが判明。これにより、データ漏洩やプライバシー侵害のリスクが懸念された
Zoom最新のセキュリティ対策
これらのセキュリティ問題は、Zoomが急速に普及するなかで、セキュリティ対策が遅れたこと原因だと考えられます。しかし、Zoomはこれらの問題を深刻に受け止め、早急な対策に乗り出しました。また、ユーザー側もZoomのようなツールに慣れておらず、必要な対策を講じていなかったことも影響しています。
ここでは、Zoomが対応したいくつかのセキュリティ対策のうち、代表的なものをまとめます。
- 暗号化の強化:Zoomは、エンドツーエンドの暗号化を導入し、会議中のデータの安全性を大幅に向上させたことにより、第三者によるデータの傍受や解読が困難になった
- プライバシー保護機能の強化:待機室機能、会議パスワード、参加者の管理機能など、プライバシー保護機能を強化。これにより、会議の主催者は参加者をより厳密に管理し、不正なアクセスを防ぐことができるようになった
- セキュリティアップデートの継続:セキュリティ脆弱性の修正や新機能の追加など、定期的なアップデートを実施している。そのため、常に最新バージョンを使用することで、セキュリティリスクを最小限に抑えることができる
- データセンターの改善:ユーザーのデータが常に適切なデータセンターを経由するようにルートの改善が行われた結果、意図しない国への接続のリスクが大幅に減少した
こうしたZoomのセキュリティ対策の拡充に加えて、ユーザー側が適切な対策がことで、安全なオンラインコミュニケーションを実現できるようになっています。
ユーザー側の対策
- 常に最新バージョンを使用する:セキュリティアップデートを適用することで、最新のセキュリティ対策を享受できる
- 待機室機能やパスワード設定を活用する:これらの機能を活用することで、会議への不正なアクセスを防ぐことができる
- ミーティングIDやURLを適切に管理する:IDやURLの共有範囲を限定し、不審なリンクには警戒を怠らない
- セキュリティ意識を高める:不審な参加者や挙動に注意し、セキュリティに関する最新情報を常に把握する

執筆者
株式会社MU 代表取締役社長
山田 元樹
社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。